東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年4月18日
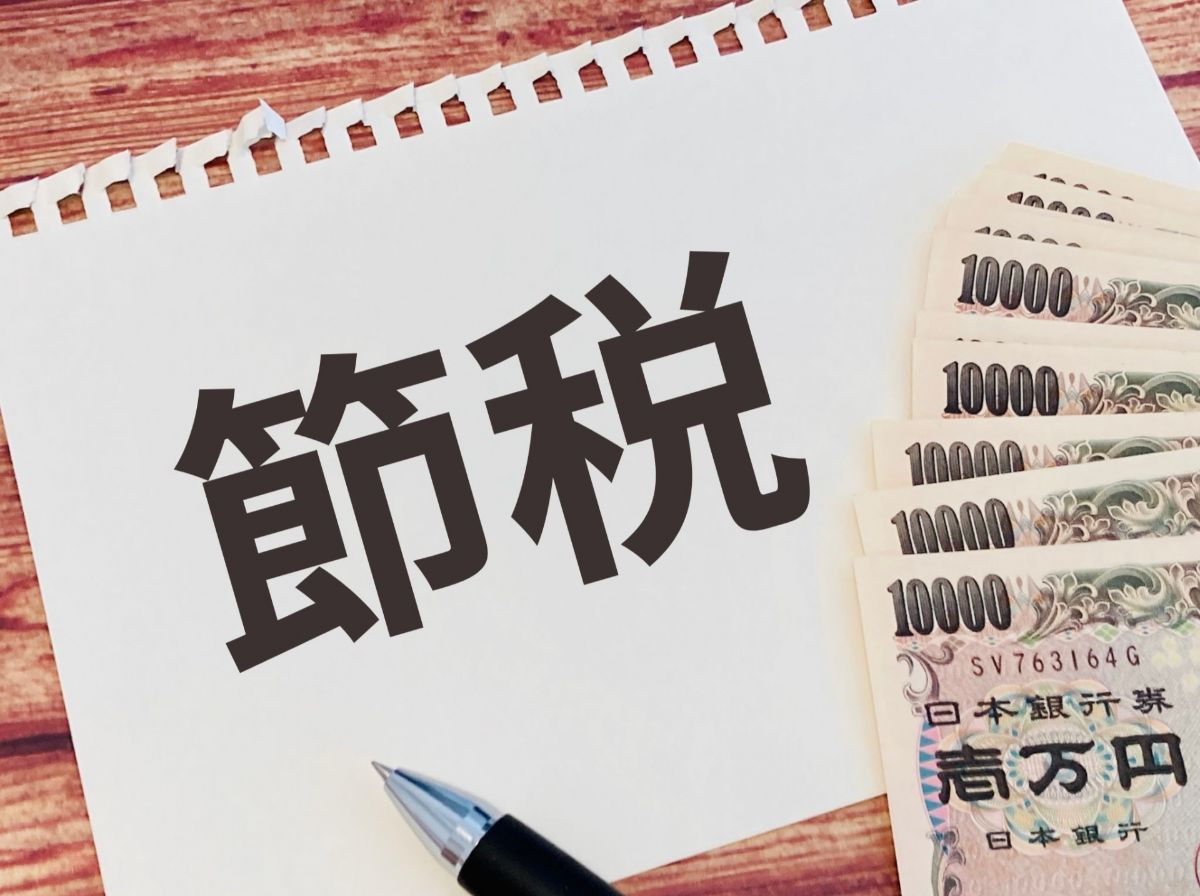
不動産を売却する際に、税金の額を見て驚いたことはありませんか。
売却益に対する譲渡所得税や住民税、さらには復興特別所得税などが加算され、思ったよりも手元に残る金額が少なかった…というケースは少なくありません。とくに近年では、不動産価格が高騰傾向にあるため、課税対象となる所得額も増えやすく、税務署からの確認や「お尋ね」が届く事例も増加しています。
「どうすれば正当に節税できるのか」「3000万円特別控除や空き家特例は自分にも適用できるのか」といった疑問を持つ方も多いはずです。また、節税に失敗すれば、無申告加算税や延滞税などで数十万円以上の損失につながることもあり得ます。
不動産売却における損失回避のヒントを、ここから一緒に見つけていきましょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産を売却する際には、売却益に対して複数の税金が課されます。多くの方が「不動産を売ったときの税金はいくらなのか」「税金が高額になるのでは」と不安を抱きますが、実際のところ税金の種類と仕組みを正しく理解することで、過剰な心配は不要です。現在、不動産売却時にかかる主な税金は以下の3つです。
売却益にかかる税金の種類と割合は以下の通りです。
| 税金の種類 | 内容 | 税率(長期譲渡) | 税率(短期譲渡) |
| 譲渡所得税 | 所得税法に基づき、譲渡益に課税 | 15% | 30% |
| 住民税 | 地方自治体に納める地方税 | 5% | 9% |
| 復興特別所得税 | 所得税の2.1%相当(加算税) | 約0.315% | 約0.63% |
譲渡所得税は、売却により発生した利益に課税される国税であり、保有期間が5年超(長期譲渡所得)か5年以下(短期譲渡所得)かによって税率が異なります。長期保有の方が税率は大幅に優遇されているのが特徴です。
加えて、復興特別所得税は2013年から導入されており、2037年までは継続が予定されています。これは東日本大震災の復興財源として導入された特別税で、譲渡所得税に加算される形で課税されます。
ここで注意したいのは、税率が単に適用されるわけではなく、「譲渡所得」という課税所得に対して適用される点です。つまり、実際に得た売却価格に対して課税されるのではなく、「取得費や譲渡費用を差し引いた後の利益」に対して課税されるということです。
多くの方が誤解しがちなポイントは、不動産売却益がすべて課税対象になると思ってしまう点です。しかし、取得時の購入費や不動産仲介手数料、登記費用、建物の解体費用、印紙税などを差し引くことで、課税対象額は大きく変わります。
不動産売却に伴う課税の中核となるのが「譲渡所得」です。これは単に不動産を売却した価格から税金がかかるのではなく、利益部分のみに課税される制度となっています。読者の多くが「譲渡所得って何?」「どうやって計算するの?」という疑問を持っているため、ここではその計算方法を明確に解説します。
譲渡所得は以下の式で算出されます。
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費 + 譲渡費用)
取得費とは、不動産を購入した際にかかった金額(本体価格・仲介手数料・登記費用・不動産取得税など)を指し、譲渡費用は売却にかかる費用(不動産仲介手数料・測量費・解体費・立退料など)です。
なお、取得費が不明な場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として認める制度もありますが、この方法では本来の取得費よりも少なく見積もられるケースが多く、結果として課税額が増えるリスクがあります。
また、建物については減価償却が適用されます。これは使用年数に応じて価値が減ることを考慮した制度で、建物部分の取得費は耐用年数に基づいて一定割合で控除されます。たとえば木造住宅で築30年の場合、建物価値はほぼゼロと見なされることもあるため、取得費の調整が必要です。
不動産を売却したからといって、必ず税金が発生するとは限りません。特定の条件を満たすことで、譲渡所得が非課税になったり、大幅に控除される特例が用意されています。ここでは利用可能な主な非課税・免税措置について詳しく解説します。
最も代表的なのが「居住用財産の3,000万円特別控除」です。この制度を適用すれば、譲渡所得から最大3,000万円までを控除でき、控除後の所得がゼロになれば税金も発生しません。
3,000万円控除の適用条件(主なもの)
また、相続した空き家に対しても「被相続人居住用財産の譲渡所得の特別控除」が認められています。これは亡くなった親などの空き家を相続し、耐震改修または取り壊したうえで売却した場合に、3,000万円までの控除が適用される制度です。
税金がかからない主なケース一覧
| ケース | 税負担の有無 | 内容の説明 |
| 3,000万円特別控除の適用 | 非課税または軽減 | 居住用不動産売却で最大3,000万円の譲渡所得を控除可能 |
| 被相続人の空き家特例の適用 | 非課税または軽減 | 一定条件を満たす相続不動産に対して控除適用可能 |
| 譲渡損失が出た場合 | 非課税 | 所得がマイナスであれば課税対象外となる |
| 所有期間が長期で控除・軽減税率適用 | 軽減 | 10年超の所有で税率が軽減され、実質課税額が少なくなる |
重要なのは、これらの制度はいずれも「確定申告が必須」である点です。特例があるにもかかわらず、申告を怠ったために控除が認められなかった例は少なくありません。適用条件を確認し、必要な書類を事前に準備しておくことが、節税の成否を分けるカギとなります。
不動産の売却益に税金がかからない条件を理解し、上手に制度を活用することで、節税対策は確実に実現可能です。特に高額な物件や相続不動産の売却では、数百万円単位で税負担が変わることもあり、制度の理解と正確な手続きが極めて重要となります。
不動産を売却したときに発生する税金の額を大きく左右するのが「取得費」です。この取得費を正しく把握し、適切に計上できるかどうかが節税の成否を左右するといっても過言ではありません。取得費の考え方は一見シンプルに見えますが、実際には多くの費用が関係しており、注意を要するポイントがいくつもあります。
まず、取得費とは、過去に不動産を取得した際にかかった費用全般を指します。ただし、不動産の価格そのものだけではなく、以下のような付随費用も含めることができます。
取得費に含まれる主な費用一覧
| 項目名 | 内容の詳細 |
| 購入代金 | 土地や建物を取得した際に売主に支払った金額 |
| 登記費用 | 所有権移転登記や抵当権設定に伴う司法書士報酬等 |
| 不動産取得税 | 不動産購入に際して都道府県に支払う地方税 |
| 仲介手数料 | 不動産会社へ支払った仲介手数料(消費税込) |
| リフォーム費用 | 増改築や内装工事にかかった費用(建物資産に組み込むもの) |
| 測量費用 | 境界確認や地積測量にかかる費用 |
これらは原則として領収書や契約書などの証憑が必要となります。取得費を正確に申告するには、これらの資料を保存しておくことが非常に重要です。
また、取得費が不明な場合、税法上は「概算取得費」として、譲渡価格の5%を取得費として認める措置があります。ただし、これを適用すると実際よりも取得費が少なくなり、その分課税される譲渡所得が多くなるため、税額が高くなる傾向があります。たとえば4,000万円で売却した不動産であれば、概算取得費は200万円にしかならず、本来の取得費が1,500万円だった場合と比べて大きな税負担となる可能性があります。
相続で取得した不動産の場合は、被相続人が購入した時点の価格が取得費となります。そのため、被相続人が取得時の資料を保管していたかどうかも、重要なポイントになります。
不動産売却時の節税を図るうえで、「譲渡費用」の正確な計上も見逃せない要素です。譲渡費用とは、売却を行うにあたって直接かかった費用のことを指し、取得費とは区別されます。これを正しく把握し、適切に経費として差し引くことで、課税対象となる譲渡所得を大きく減らすことができます。
譲渡費用に含まれる主な費用項目は以下の通りです。
譲渡費用に該当する具体的な支出例
| 費用項目 | 説明 |
| 仲介手数料 | 不動産会社に支払う売却仲介の報酬 |
| 測量費用 | 境界確認や地積確定のために行った測量にかかる費用 |
| 建物解体費 | 古屋付き土地売却のために行った解体作業費 |
| 建物取り壊し補償 | 借主への立ち退き料など |
| 登記費用 | 所有権移転や抵当権抹消にかかる司法書士報酬等 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付した印紙にかかる税金 |
| 広告費 | 売却を促進するための広告掲載や宣伝費 |
| 契約解除に伴う違約金 | 売却のために旧契約を解除し、違約金を支払った場合 |
上記以外にも、「売却に必要であったことを客観的に説明できる支出」であれば、譲渡費用として認められる可能性があります。ただし、認められるかどうかの判断は税務署によって異なる場合があるため、税理士への事前相談が推奨されます。
また、以下のような費用は譲渡費用として認められないので注意が必要です。
譲渡費用に該当しない費用の一例
実務では、不動産売却に際して「どの費用が取得費か、どの費用が譲渡費用か」を混同して申告するケースがよく見られます。これにより申告漏れや過大申告が生じ、税務署からの問い合わせ対象となることもあります。すべての費用に対して領収書や契約書などのエビデンスを整備しておくことが、スムーズな節税と正確な申告の鍵になります。
建物付き不動産を売却する際に避けて通れないのが「減価償却」の理解です。減価償却とは、建物などの資産が時間の経過とともに価値が減少していくことを考慮し、その減少分を費用として計上する会計・税務上の制度です。節税において重要なのは、建物の取得費はそのまま全額が経費になるわけではなく、「減価償却後の価値」で譲渡所得を計算する点にあります。
減価償却費の計算には「定額法」が用いられ、主に以下の要素が関係します。
減価償却費の計算式は以下の通りです。
減価償却費 = 建物取得費 × 償却率 × 経過年数(または月数)
建物構造ごとの耐用年数と償却率(定額法)
| 構造 | 耐用年数 | 償却率(定額法) |
| 木造 | 22年 | 約0.046 |
| 軽量鉄骨造 | 27年 | 約0.038 |
| 鉄筋コンクリート | 47年 | 約0.022 |
計算例として、築10年の木造住宅を2,000万円で取得した場合を考えます。
減価償却費の概算例
建物取得費 2,000万円
償却率 0.046
経過年数 10年
減価償却費=2,000万円 × 0.046 × 10年 = 920万円
この場合、建物の取得費として残るのは1,080万円(2,000万円−920万円)となり、譲渡所得の計算にはこの残存価額を用います。
重要な注意点として、減価償却は「実際に費用として計上していなかった場合」でも、税務上は自動的に償却されたものと見なされます。つまり、償却を行っていなかったからといって、取得費を全額経費とすることはできないということです。
法人が不動産を売却する際には、個人とはまったく異なる税務処理が求められます。特に所得の区分、課税方式、控除の有無などに明確な違いがあり、誤解やミスが生じると過大な納税につながるおそれがあります。以下に、法人と個人の税制上の違いを分かりやすく比較した表を掲載します。
| 比較項目 | 法人 | 個人 |
| 所得の区分 | 事業所得として法人税課税 | 譲渡所得として所得税・住民税課税 |
| 控除の適用 | 一部経費計上は可能(控除ではない) | 3000万円特別控除、所有期間による軽減措置等 |
| 損益通算 | 可能(事業年度内で調整) | 制限あり(他の所得との通算に条件あり) |
| 税率 | 一律(法人税率) | 所得金額・保有年数により変動(累進課税) |
| 節税の自由度 | 高い(経費処理や役員報酬等で調整可) | 制限あり |
法人が不動産を売却する場合、その譲渡益は法人所得に含まれ、法人税の課税対象となります。これに対して、個人の場合は譲渡所得という別のカテゴリに分類され、所有期間に応じて短期・長期の区分により異なる税率が適用されます。個人に認められる「居住用財産の3000万円控除」や「軽減税率の特例」などは、法人には一切適用されません。
この違いから見えてくるのは、法人売却は損金処理や役員報酬調整、節税スキームを柔軟に活用できる反面、特例制度がないため精緻な利益調整が必要であるという点です。法人代表者が個人と法人のどちらで保有・売却すべきかを判断する場合には、今後のキャッシュフローや保有資産の管理方針と合わせて検討すべきです。
法人が不動産を売却して得た利益には、一般的な法人税に加え、一定の条件下で「土地重課税(譲渡益重課制度)」が適用されるケースがあります。これは法人が所有する土地を短期間で売却し高額な譲渡益を得た際に課税強化される制度で、不動産投資法人や土地転がしを想定した対策です。
損益通算の観点では、法人の場合、その年度の赤字と譲渡益を相殺して課税所得を軽減できる可能性があります。具体的には、他の不動産事業の赤字や本業の損失などと損益を通算し、結果として法人税の圧縮につなげる節税策が活用されます。赤字が大きい年度で売却を実行することで、最小限の税負担で資産を手放せる可能性が高まります。
さらに、法人には「欠損金の繰越控除」という制度も存在します。これは過去に発生した赤字(欠損金)を将来10年間(一定条件下)にわたって繰越し、黒字が出た年度の利益と相殺できる制度です。不動産売却による黒字と過去の欠損金を通算できれば、実質的な課税を回避できるため、戦略的に活用すべき制度と言えるでしょう。
法人は個人とは異なり、複数の年度にまたがる損益調整が可能です。しかし制度適用には厳格なルールがあり、単年度黒字の平準化、連結納税制度の適用可能性なども加味したうえで総合的な税務戦略が求められます。
法人が不動産を売却する際、見落としがちな論点が「消費税」の課税対象・非課税の判断です。消費税は通常の商品やサービスに課税されるものですが、不動産の売却においては特例が適用されるため、正しい理解が必要です。
まず原則として、「土地の譲渡は非課税」「建物の譲渡は課税対象」となります。つまり、法人が所有する物件を売却する際に、土地部分の代金は消費税がかからず、建物部分のみに消費税が課税される仕組みです。このため、売却価格の内訳を明確に区分することが重要となります。
| 不動産の種類 | 消費税の課税有無 | 備考 |
| 土地 | 非課税 | 課税仕入れとの控除対象外 |
| 建物 | 課税対象 | 売却時に消費税の納税義務発生 |
| 区分所有物件 | 建物部分のみ課税 | 管理費・修繕積立金にも注意 |
また、法人が「課税事業者」として登録されているかどうかでも処理が変わります。課税売上高が基準以下の中小法人の場合、「免税事業者」として消費税の納付義務がないこともありますが、これにより仕入税額控除が使えなくなるため、逆に不利になるケースもあります。
消費税の扱いで特に注意すべき点は、次の通りです。
このように、法人による不動産売却では消費税の取り扱いも重要な節税ポイントの一つです。消費税に関する法令や通達は改正も多く、最新の情報を税理士と共有しながら判断することが求められます。
税務署からの「お尋ね」とは、不動産売却などに伴い発生した収入について、正しく申告されているかを確認するために送付される文書のことです。これは税務調査の前段階として位置付けられ、放置した場合は本格的な調査に発展する可能性があるため、慎重な対応が求められます。
共通するのは、「申告の信憑性に疑義がある」または「課税漏れの可能性がある」と税務署が判断する状態です。
では、こうしたリスクを未然に防ぐためには何が必要なのでしょうか。以下に主な予防策を整理します。
| 項目 | 内容 | 実行時期 |
| 取得費や譲渡費用の根拠資料を保管 | 登記簿謄本、領収書、契約書など | 売却後すぐ |
| 確定申告書を正確に作成 | 譲渡所得税・住民税などの内訳を明記 | 申告時 |
| 税理士と相談 | 課税額の妥当性を第三者視点で確認 | 売却前後どちらでも可 |
| 不明点がある場合は税務署に事前確認 | 疑問点を自己判断で進めない | 随時対応 |
加えて、「お尋ね」には回答義務がありませんが、無視することは強く避けるべきです。誠意を持って対応し、書類を提出することが望ましいとされています。これにより税務署との信頼関係を保ち、調査への発展を防ぐことが可能になります。
注意すべきは、不動産売却が単発の取引であっても、金額が大きくなると「副業」や「事業所得」とみなされる可能性がある点です。譲渡所得として正しく申告するには、収入だけでなく支出、つまり取得費や経費についても明確な記録が必要となります。
節税の意識が高まる中で、知らず知らずのうちに「脱税」と疑われる不自然な節税手法に踏み込んでしまうケースが増えています。不動産売却に関しても、正しく節税しているつもりでも、税務署の視点では不自然と判断されてしまう可能性があるため注意が必要です。
特に以下のようなケースは税務署が目を光らせるポイントとなっています。
これらのリスクを避けるためには、下記のような対応が求められます。
| リスク内容 | 税務署が疑うポイント | 防止策 |
| 不当に安い売却価格 | 実勢価格と乖離している | 路線価・査定書を保管 |
| 取得費が過大 | 領収書や契約書の欠如 | 出費ごとに明細管理 |
| 実体のない費用 | 工事写真や業者との契約なし | 第三者の証拠を準備 |
| 控除の誤用 | 適用年や条件に該当しない | 国税庁の条件を確認 |
「これくらいならバレないだろう」「他の人もやっているから大丈夫」といった安易な考えは通用しません。合法的な節税と違法な脱税は、紙一重の部分も多く、実際には専門家と相談しながら進めることが重要です。
不動産売却を成功させるためには、手続きの初期段階から必要書類を正確に整えることが極めて重要です。書類の不備や準備の遅れは、取引の遅延やトラブルを招く原因となるため、事前の確認が求められます。不動産の種類や売却形態によって準備すべき書類が異なるため、網羅的な知識と実務に即した判断力が不可欠です。
まず代表的な必要書類のひとつに、不動産の登記事項証明書があります。これは法務局で取得できるもので、物件の所有者情報や面積、抵当権の有無などが記載されています。最新情報でなければならず、取得から3カ月以内のものであることが求められるのが一般的です。また、固定資産税評価証明書も必要となります。これは市区町村の役所で発行され、不動産の評価額を確認するために使用されます。評価額は譲渡所得計算や登記費用の算出に影響するため、売買契約前に正確な金額を把握しておく必要があります。
さらに、本人確認書類の提出も求められます。一般的には運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどのうち、顔写真付きの公的身分証明書が必要です。法人が売却する場合は登記簿謄本や印鑑証明書、代表者の本人確認書類も必要となります。これらの書類が不足していると、契約の締結ができないことがあるため、事前にリストアップして準備を整えることが肝心です。
一戸建てやマンションなどの種類によっては、さらに追加で必要となる書類も存在します。例えばマンションの場合、管理規約や管理費の支払い状況が確認できる書類、管理組合から発行される証明書などが求められるケースがあります。これにより、買主は将来的な管理体制や費用について正確に把握できます。
これらの書類を漏れなく準備することは、不動産売却の成否を分ける鍵となります。特に近年は電子契約やリモート取引の増加により、書類のデジタル化が進んでいますが、それでも原本の提出が必要な場面は多いため、原本とコピーの両方を用意しておくとスムーズです。また、売却前の準備段階から、これらの書類がきちんと保管されているかを点検し、不足している場合には早急に取得手続きを行うことが推奨されます。
不動産売却を進めるうえで、信頼できる専門家の力を借りることは極めて重要です。とはいえ、「税理士と司法書士の違いがよく分からない」「不動産会社をどう選べばいいのか迷う」といった声も多く聞かれます。それぞれの役割や専門性を理解し、適切なタイミングで相談・依頼することが、スムーズな売却とトラブル回避につながります。
まず、税理士は主に税務に関する業務を担う専門家です。不動産売却時には「譲渡所得の計算」「税金の申告」「特別控除や軽減措置の適用判断」などの分野で力を発揮します。特に売却益が発生した場合、所得税や住民税の申告義務が生じるため、正確な計算と節税対策が不可欠です。譲渡益が高額であればあるほど、税理士の助言によって合法的に節税できる可能性が高まります。また、贈与税や相続税の兼ね合いがあるケースでも、総合的な税務アドバイスを受けられる点が大きな利点です。
一方、司法書士は法律に基づく不動産の登記を専門とする国家資格者です。不動産の所有権移転登記や抵当権抹消登記など、登記手続きに関する法的な事務を正確かつ迅速に処理する役割を担っています。売却に際して登記内容が古かったり、複数の名義人がいたりする場合には、司法書士のサポートが不可欠となります。また、成年後見制度の活用や遺産分割協議が関係する売却でも、法的な整備が必要な場面で大きな力となります。登記漏れや誤記入は取引無効の原因にもなるため、専門的知識が求められる領域です。
不動産会社は、売却活動の実務をトータルで支援する存在です。物件の査定、販売戦略の策定、広告掲載、内覧対応、交渉、契約書作成など、多岐にわたる業務を一手に担います。特に地域密着型の業者や、大手で広範なネットワークを持つ業者など、それぞれに特徴があるため、物件の所在地や売却目的に応じて最適な業者を選ぶことが成功の鍵となります。また、不動産会社によっては自社で買取を行っているケースもあり、スピード重視の売却を希望する場合に適しています。ただし、仲介手数料の取り扱いや査定額と成約価格の差異については、事前に十分な説明を受けるべきです。
これらの専門家のうち、誰にどの段階で相談すべきかは、売却の背景や状況によって異なります。たとえば、物件の相続や贈与に関する経緯がある場合は、司法書士や税理士に先行して相談するのが適切です。一方で、売却活動自体を円滑に進めるためには、不動産会社との連携が不可欠です。また、すべての専門家が連携してくれる体制の整ったワンストップ型のサービスを提供する会社も増えており、時間と手間を減らす選択肢として注目されています。
不動産の売却に伴う税金は、想像以上に複雑で見落としがちなポイントが多く存在します。譲渡所得税や住民税、復興特別所得税などの負担を正しく理解し、節税対策を講じることは、最終的に手元に残る金額を大きく左右します。
たとえば、3000万円の特別控除や空き家の特例を活用すれば、条件次第で数百万円単位の税額を圧縮できる可能性があります。一方で、制度を誤って適用したり、手続きや提出期限を守れなかった場合には、節税どころか追徴課税や加算税の対象となるリスクも否定できません。
こうしたリスクを回避し、正当に節税を進めるには、売却前の準備と情報収集が不可欠です。必要書類の整備、適切なタイミングでの専門家相談、そして正確な税額のシミュレーションは、どれも抜かりなく対応しておきたい基本です。
不動産売却は一生に何度も経験することではありません。だからこそ、正しい知識と手順に基づいて行動することが、損失を避け、利益を最大限に活かす鍵となります。税金という大きなコストを、あなた自身の判断と準備で最小限に抑えましょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
Q. 不動産を売却したときにかかる税金はいくらぐらいが相場ですか?
A. 不動産売却時に課税される税金は主に譲渡所得税、住民税、復興特別所得税の三つで構成されており、譲渡益の約20.315パーセントが基本的な課税額となります。たとえば1000万円の譲渡益が出た場合、約203万円程度が税金として発生します。さらに売却金額や保有期間、控除の適用有無によって金額は大きく変動するため、事前の税金計算が極めて重要です。
Q. 節税のために取得費や譲渡費用を多く計上することは本当に効果がありますか?
A. はい。取得費には購入代金のほか、登記費用やリフォーム費用なども含めて正確に計上することで、譲渡所得が大幅に減り、その分課税額も下がります。たとえば取得費が500万円増加した場合、約100万円以上の税負担が軽減されるケースもあります。建物解体費や仲介手数料なども譲渡費用に含まれるため、領収書や契約書を整理しておくことが節税への第一歩です。
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。