東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年9月12日
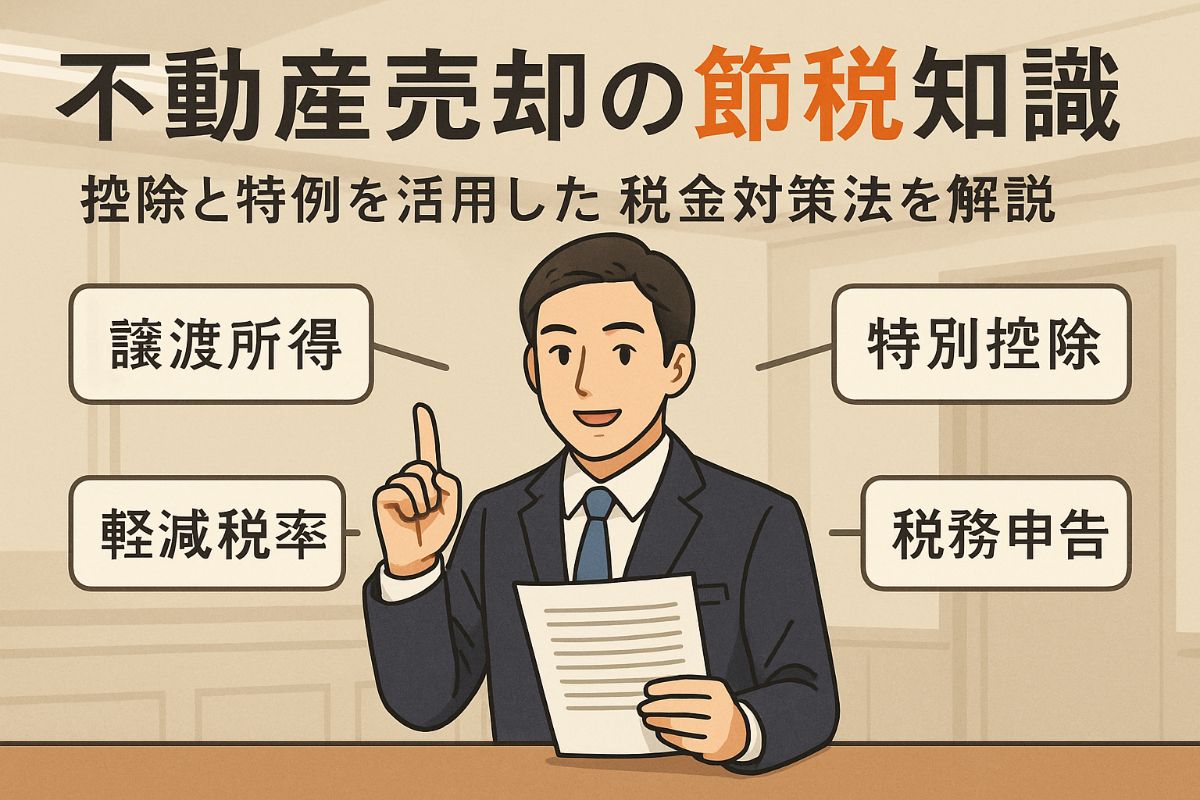
「不動産を売却すると、想定外の税金が発生して利益が目減りするのでは…」と不安に感じていませんか?実際、不動産売却時には譲渡所得税・住民税・印紙税など【3種類以上】の税金が関わり、税率や控除の条件によって納税額は大きく変動します。たとえば、マイホーム売却で3,000万円特別控除を活用できれば、課税額を大幅に軽減でき、控除適用の有無で【数百万円単位】の差が生まれることも珍しくありません。
しかし、税金の仕組みや特例の条件は複雑で、申告ミスや計算誤りによって本来より多く支払ってしまうケースも。強調したいのは、「正しい知識と準備で、税負担を最小限に抑える方法が必ずあります」という点です。
税制は毎年見直されており、現在も細かな改正が進んでいます。最新の制度や控除の活用法を知らずに進めると、大きな損失につながる可能性もあります。
この記事では、不動産売却にかかる税金の全体像、節税効果の高い特例・控除、具体的な計算方法、そして失敗しないための実践ノウハウまで、専門家監修のもとで詳しく解説。「最後まで読むことで、あなたの不動産売却を安心・確実に進めるための知識と具体的な節税ポイント」が手に入ります。悩みや疑問を解消し、賢く税負担を減らす第一歩を踏み出しましょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却を行う際には、さまざまな税金が関わります。売却益が出た場合に課税される所得税や住民税、売買契約書に必要な印紙税、登記時にかかる登録免許税などが代表的です。これらの税金を正しく理解し、適切な節税対策を講じることで、税負担を大きく軽減できます。特に3,000万円特別控除や長期譲渡所得の優遇税率、相続不動産の売却に関する特例など、状況に応じた制度を活用することが重要です。また、確定申告の手続きや申告義務の有無についても事前に確認しておく必要があります。
不動産売却時に発生する主な税金は以下の通りです。
| 税目 | 説明 |
|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却益に対して課税。所有期間によって税率が変動します。 |
| 住民税 | 譲渡所得税とセットで課税される地方税。 |
| 印紙税 | 売買契約書の作成時に必要な税金。契約金額により税額が変わります。 |
| 登録免許税 | 不動産登記変更の際に必要な税金。 |
ポイント一覧
譲渡所得税は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた「譲渡所得」に課税されます。計算式は以下の通りです。
所有期間により税率が異なり、
取得費には購入金額や仲介手数料、登記費用などが含まれます。 譲渡費用には売却時の仲介手数料や測量費用などが該当します。
売買契約書には必ず印紙税が課され、契約金額に応じて税額が決まります。また、不動産の名義変更時には登録免許税が必要です。
| 契約金額 | 印紙税額 |
|---|---|
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
登録免許税は、土地・建物ごとに税率や算定基準が異なり、所有権移転登記の場合、評価額×2%(軽減措置あり)が一般的です。これらの費用も売却時の経費として計上できます。
不動産売却に伴う税金は、売却した年の翌年に確定申告を行い納税します。税金が発生するのは「売買契約の成立し、代金が支払われた時点」です。会社員や年金受給者でも、売却益が発生した場合は必ず申告が必要です。特例や控除を受ける場合も同様に申告が求められます。
確定申告には以下の手順が必要です。
申告書類や計算が複雑な場合は、税理士や専門家に相談することでミスを防げます。最近では電子申告(e-Tax)も利用可能で、スマートフォンでも手続きが簡単になっています。
居住用財産を売却した場合、一定の条件を満たすと譲渡所得から最大3000万円の特別控除が適用されます。この控除により、多くのケースで課税所得が大幅に減少し、税負担を抑えられます。
適用要件は主に以下の3点です。
控除額は「譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用」から最大3000万円まで差し引くことができます。例えば、譲渡所得が2500万円なら全額控除され、課税所得は0円になります。
申告時の注意点として、確定申告が必須であり、必要書類や計算方法の確認を怠らないようにしましょう。
この3000万円特別控除には再利用禁止規定があります。過去2年以内に同じ特例を利用している場合は、再度適用できません。また、親子間や夫婦間での売却、贈与に近い取引では適用除外となります。
特例の利用履歴は税務署で管理されており、複数回の適用はできませんので、売却のタイミングや将来の計画を事前に確認することが大切です。
自宅を売却して新たなマイホームを購入する場合、買換え特例を利用することで譲渡所得税の支払いを繰り延べることができます。この特例は、売却益が発生しても新たな住宅の購入価格が一定以上の場合、税金の支払いを次回の売却時まで先延ばしできるのが最大のメリットです。
買換え特例の主な条件は以下の通りです。
この特例を活用することで、資金繰りを改善しつつ将来の税負担に備えることが可能です。
買換え特例の適用には売却と購入のタイミングが重要です。売却した年の前年1月1日から翌年12月31日までの3年間に新居を購入する必要があります。また、新居は「自己居住用」であることが条件です。
対象となる物件の要件は次の通りです。
これらを満たさない場合、特例の適用は認められません。
不動産売却における譲渡所得税率は「所有期間」により異なります。所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、より低い税率が適用されます。逆に5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率が高くなります。
所有期間を意識し、5年を超えてから売却することで節税効果が期待できます。売却のタイミングは税額に大きく影響するため、計画的な検討が重要です。
所有期間は「取得日から売却契約締結日まで」で計算します。取得日は通常は「登記日」となりますが、相続や贈与の場合は被相続人など前所有者の取得日を引き継ぐケースがあるため注意が必要です。
この期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わるため、売却前に必ず確認しましょう。
不動産売却時に課税される譲渡所得税の計算では、取得費を正確に算出することが節税への第一歩です。取得費には、購入代金だけでなく、仲介手数料や登録免許税、印紙税、司法書士報酬などの諸費用が含まれます。加えて、建物の場合は減価償却費の考慮が必要です。下記に主な取得費の項目をまとめます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 購入代金 | 不動産の購入価格 |
| 仲介手数料 | 不動産会社への手数料 |
| 登録免許税・印紙税 | 登記・契約時の税金 |
| 減価償却費 | 建物部分の減価償却分 |
ポイント
建物の取得費は、購入価格から減価償却費を差し引いた金額となります。減価償却は、所有期間と建物の構造ごとに異なる耐用年数・償却率が適用されます。例えば、木造住宅の場合、法定耐用年数は22年です。所有期間が長いほど減価償却額が大きくなり、実際の取得費は減少します。
計算例
このように、建物の取得費は減価償却後の金額となるため、適切な計算が必要です。
譲渡費用は、不動産売却時に直接必要となった経費が対象です。主な例としては、仲介手数料、建物の解体費用、リフォーム費用、測量費、契約書の印紙税などがあります。これらをしっかりと計上することで、課税対象となる譲渡所得を減らすことができます。
| 譲渡費用の例 | 内容 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売却時に支払う手数料 |
| 測量費 | 境界確定等のための費用 |
| 解体費用 | 古家付き土地売却時の解体費用 |
| リフォーム費用 | 売却目的の修繕費等 |
| 印紙税 | 売買契約書に貼付する印紙 |
ポイント
譲渡費用として計上するには、支払いを証明する書類の保存が必須です。領収書、請求書、契約書など、経費項目ごとに分けて整理しましょう。税務調査時に証明できなければ、経費として認められない場合があります。
証明書類の保存方法チェックリスト
しっかりと証拠を残すことで、節税効果を最大化できます。
取得費がどうしても分からない場合、譲渡収入の5%を取得費とみなす「概算取得費」の特例が適用されます。しかし、実際の取得費が分かる場合と比べて税負担が大きくなる傾向があるため、可能な限り資料を探して実費で計算することが推奨されます。
概算取得費のポイント
不動産売却にともなう確定申告は、以下のケースで必要かどうかが判断されます。
| ケース | 申告の要否 | ポイント |
|---|---|---|
| 売却益が発生(譲渡益あり) | 必要 | 税金が発生するため必ず申告が必要 |
| 売却損失が発生(譲渡損あり) | 場合による | 損益通算や繰越控除の活用目的で申告することで節税効果を得られる |
| 特別控除(3,000万円控除等)適用 | 必要 | 控除の適用を受けるには必ず申告が必要 |
| 相続や贈与で取得し売却 | 必要 | 取得費計算や税務対応が複雑なため専門家相談も推奨 |
| 売却益・損失いずれもなく譲渡所得ゼロ | 不要 | 税金が発生しない場合は申告不要 |
ポイント: 多くの場合、売却益の有無にかかわらず節税や控除を受けるためには申告が必要です。売却した不動産がマイホームや相続物件の場合、特別控除や優遇税制の条件確認も重要です。
譲渡所得がマイナス(赤字)となった場合でも、確定申告を行うことで以下のメリットがあります。
メリット
デメリット
活用のポイント
注意: 申告不要とせず、損益通算・繰越控除を賢く活用して将来の税負担を軽減することが可能です。
不動産売却に関する確定申告では、申告書Bと「分離課税用の譲渡所得の内訳書」が必要です。
申告手順
提出方法
記入例
| 項目 | 記入内容例 |
|---|---|
| 譲渡収入金額 | 売却価格(例:3,000万円) |
| 取得費 | 購入価格+取得時費用 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料、印紙代など |
| 控除額 | 3,000万円特別控除等 |
ポイント: 記入漏れや添付書類の不足は税務調査の原因となるため、確実に確認しましょう。
不動産売却の申告で多いミスと、回避策を整理します。
回避策: チェックリストを作成し、申告前に一つずつ確認することが有効です。
税務調査は、申告内容に不明点や誤りがある場合に行われます。事前準備として下記を徹底しましょう。
ポイント: 万一の調査にも落ち着いて対応できるよう、普段から書類管理や計算内容の記録を徹底しておくことが安心につながります。
法人が不動産を売却する場合、発生する譲渡益は法人税・住民税・事業税の対象となります。特に短期譲渡の場合は、利益が一括で課税されるため、節税対策が重要です。主なポイントは以下の通りです。
相続した不動産を売却する際は、相続税の負担を軽減できる特例が複数存在します。特に「取得費加算の特例」は、相続で支払った相続税の一部を譲渡所得の取得費に加算できるため、譲渡所得税の節税に直結します。
相続税控除や特例の組み合わせによって、大幅な節税が実現できますが、期限や条件を逸すると適用できないため、計画的な売却が欠かせません。
相続不動産の節税には、売却のタイミングが非常に重要です。相続開始から3年10カ月以内に売却することで、「取得費加算の特例」が適用されます。主な条件は以下の通りです。
この特例を利用することで、譲渡所得税の圧縮が可能となり、総合的な税負担を軽減できます。期限管理と書類準備が重要です。売却計画を立てる際は、税理士など専門家への相談をおすすめします。
投資用不動産の売却で損失が発生した場合、節税に活かせる手段が複数存在します。特に、損失の繰越控除や損益通算は大きなメリットです。
投資用不動産の売却では、こうした節税策を事前に把握し計画的に活用することで、将来的な税負担を大きく軽減できます。
土地を売却する際には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税が発生します。譲渡所得は「売却金額-取得費-譲渡費用」で算出され、保有期間が5年超なら長期譲渡所得として税率が軽減されます。土地売却後の節税策としては、譲渡所得に対するふるさと納税の活用が注目されています。ふるさと納税の寄附限度額は譲渡所得の増加で上がるため、売却益が出た年は控除枠を大きく活用できることが特徴です。相続した土地を売却する場合には、3,000万円特別控除や取得費加算の特例も適用できる場合があります。
| 税目 | 概要 | 節税策 |
|---|---|---|
| 譲渡所得税 | 売却益に課税 | 保有期間5年超で税率軽減 |
| 住民税 | 一律10% | 控除の活用で負担減 |
| ふるさと納税 | 控除枠拡大 | 売却年の寄附額増加 |
土地の取得費が分からない場合、売却価格の5%を取得費とみなす「概算取得費」が利用できます。この方法は古い相続土地の売却などでよく使われます。また、相続で取得した土地の場合は、相続税評価額を取得費に加算できる「取得費加算の特例」があります。これにより、譲渡所得が圧縮され税負担が軽減されます。加えて、譲渡費用には仲介手数料や登記費用、印紙代なども含まれるため、関連費用は必ず領収書などで証拠を残しておきましょう。
マンションや戸建てを売却する場合、3,000万円特別控除の適用が大きな節税ポイントです。自宅を売却して利益が出ても、一定の条件を満たせば3,000万円まで非課税となります。さらに、売却時にかかる仲介手数料やリフォーム費用なども譲渡費用として計上でき、課税所得を減らすことが可能です。また、住宅ローン控除を受けていた場合、売却時点で残債があるなら控除の取り扱いに注意が必要です。買い替えや住み替えでは「特定居住用財産の買換え特例」も活用できます。
| 節税策 | 概要 |
|---|---|
| 3,000万円控除 | 自宅売却益が3,000万円まで非課税 |
| 譲渡費用計上 | 仲介手数料や登記費用など |
| 買換え特例 | 新居購入時の課税繰り延べ |
空き家の売却では、「被相続人の居住用財産(空き家)特例」が利用できます。相続から3年以内に売却し、一定の耐震基準を満たすか、建物を取り壊して更地で売却した場合、最高3,000万円まで譲渡所得から控除されます。注意点は、相続人が売却まで空き家を住居や事業用に使っていないことや、申告時に必要書類が揃っていることです。特例の適用漏れを防ぐためにも、売却前に条件を詳細に確認し、税理士など専門家に相談することがおすすめです。
不動産の用途によって適用される税率や特例が異なります。自宅(居住用)は3,000万円特別控除や軽減税率が利用できますが、投資用不動産や法人所有の場合はこれらが使えません。投資用物件の売却時は損益通算や繰越控除、法人の場合は簿価や損益通算、短期譲渡に対する重課税など独自の計算が必要です。このように、不動産の種類や用途に応じて最適な節税策を選ぶことが重要です。売却前に条件や特例の可否を必ず確認してください。
不動産売却で節税に成功した実例として、マイホームを売却した際に「3,000万円特別控除」を活用し、大幅に税負担を減らしたケースがあります。例えば、譲渡所得が3,500万円の場合でも、この控除を適用することで課税対象は500万円となり、税額を数百万円単位で軽減できます。下記のテーブルは主な節税策と節税額の目安をまとめたものです。
| 節税策 | 適用条件 | 節税額(目安) |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 居住用財産の売却 | 最大数百万円減税 |
| 長期譲渡所得の税率優遇 | 所有期間5年以上 | 税率20%→15%程度 |
| 買換え特例 | 居住用財産を買換え | 数十万~数百万円 |
多くの方が、売却益が出る場合でも特例や控除を組み合わせることで大きな節税効果を得ています。
節税を実現するためには、取得費や譲渡費用の正確な計上と特例の申請手続きが重要です。具体的な手順は以下の通りです。
ポイント:
節税に失敗するケースも少なくありません。主な失敗例と原因は以下の通りです。
| 失敗例 | 主な原因 | 防止策 |
|---|---|---|
| 控除・特例の申請漏れ | 確認不足・知識不足 | 事前に制度を確認 |
| 費用計上漏れ | 証憑紛失・管理ミス | 書類の徹底保管 |
| 申告書の記載ミス | 計算・手続きの複雑さ | 専門家に相談 |
申告や計算のミスは余計な納税や罰則につながるため、注意が必要です。
節税の成否は日常的な管理にかかっています。成功のために意識すべき管理法は次の通りです。
こうした日常的な積み重ねが、いざというときの節税成功につながります。
近年の税制改正では、譲渡所得や特別控除の適用条件が一部見直されています。特に、居住用財産の3,000万円控除や相続した不動産の売却に関する特例は、適用時期や要件が変更になる場合があります。
法改正によって節税効果が大きく異なることもあるため、売却前に必ず最新情報を確認し、専門家のアドバイスを活用することが重要です。
不動産売却時でも税金がかからない場合があります。代表的なのは、マイホームを売却し「3,000万円特別控除」の条件を満たした場合です。ほかにも、譲渡所得がゼロまたはマイナスになるケース、保有期間が長期で取得費や譲渡費用が売却価格と相殺され、所得が発生しない場合などが該当します。また、相続した不動産を一定期間内に売却する場合にも特例が適用され、税負担を大きく軽減できることがあります。事前に条件を確認し、不要な納税を避けることが大切です。
3,000万円特別控除は、居住用財産(マイホーム)を売却した際に利用できる制度で、以下の条件を満たすことが必要です。
これらを満たすと、譲渡所得から3,000万円が控除され、税金がかからないケースもあります。相続税の取得費加算の特例も適用できるため、納税額を抑えることが可能です。計算には証明書類が必要となるため、資料の保管を心掛けてください。
土地売却で得た譲渡所得は、ふるさと納税の控除上限額に影響します。売却益が増えると、所得税や住民税が増加しますが、ふるさと納税の控除上限も同時にアップします。これにより、より多くの寄付が可能になり、実質的な節税効果が期待できます。ただし、ふるさと納税だけで譲渡所得税が軽減されるわけではないため、シミュレーションを活用し最適な寄付額を把握しましょう。
法人が不動産を売却する際の節税ポイントは以下の通りです。
これらを徹底することで、法人税・地方税を最適化できます。
不動産売却で赤字(譲渡損失)が出た場合は、損失の扱いが重要です。居住用不動産の場合、要件を満たせば他の所得と損益通算が可能です。たとえば住宅ローン残高がある場合、一定額まで他の所得と相殺できます。法人の場合は事業所得と通算し、翌期以降に繰越控除することも認められています。申告時には根拠となる書類をしっかり準備しましょう。
不動産売却に関する確定申告を忘れた場合、速やかに「期限後申告」を行う必要があります。申告が遅れると延滞税や加算税が発生する可能性がありますが、早めに手続きをすればペナルティを最小限に抑えることができます。還付申告の場合は、5年以内であれば申請可能です。申告漏れを防ぐためにも、売却時点で必要書類を整理し、税理士などに相談することをおすすめします。
税務調査に備えるには、正確な資料の保管と帳簿管理が不可欠です。以下のポイントを意識しましょう。
これらを徹底することで、調査時のトラブルを防ぎ、税務署からの指摘にも冷静に対応できます。信頼できる専門家と連携しながら、正しい納税管理を心がけてください。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。