東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年2月15日
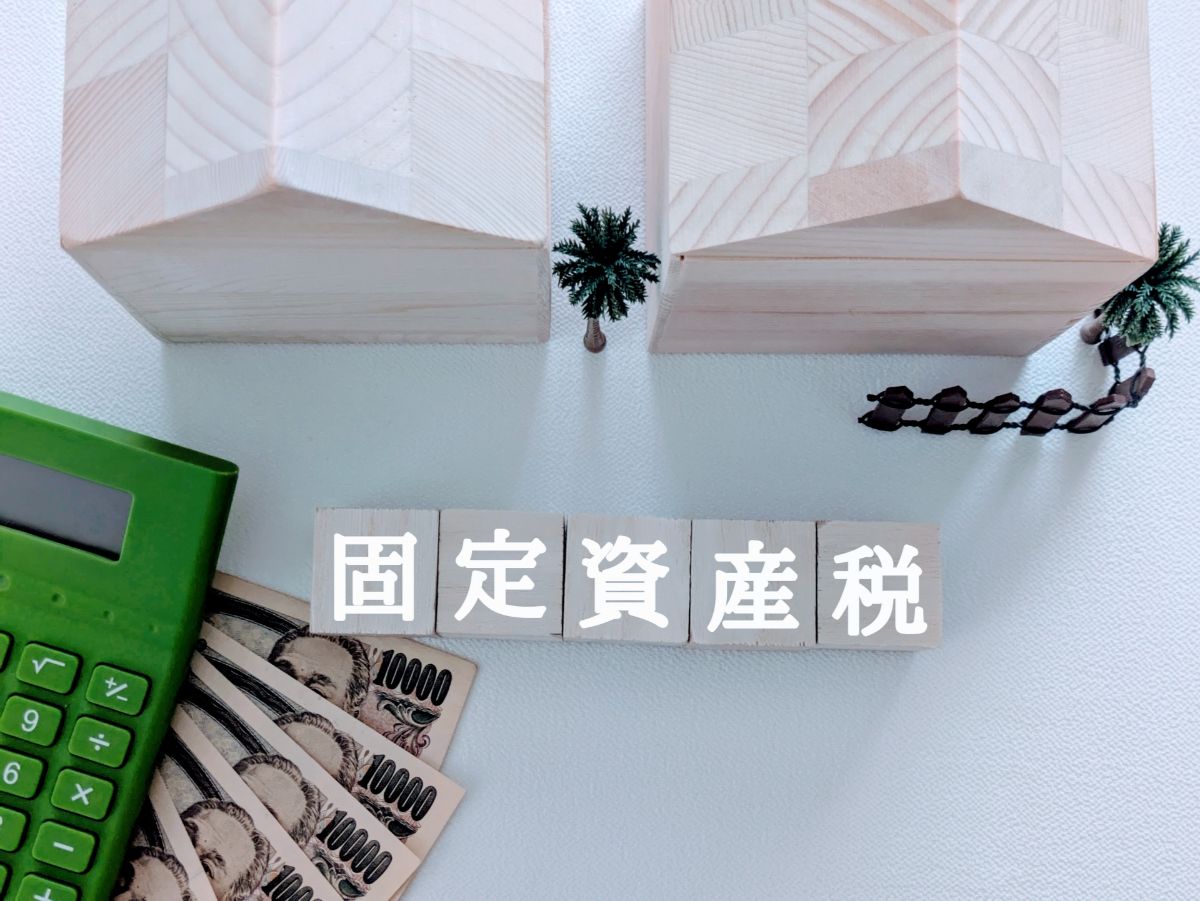
不動産を売却すると、固定資産税はどうなるのでしょうか?
「売却したら、固定資産税はもう支払わなくていい?」
「引き渡し前後の税負担はどう分担する?」
「精算方法を知らずに進めたら損をする?」
不動産売却時の固定資産税について、こうした疑問や不安を感じている方は少なくありません。特に、固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、売却したタイミングによって支払い義務や精算方法が変わります。これを誤ると、予定外の支出が発生するだけでなく、売主・買主の間でトラブルにつながることもあります。
実際に固定資産税の精算を適切に行わなかったために、追加で納税を求められたケースも報告されています。そうならないためには、正しい税額の計算方法、負担割合、売買契約書への記載事項を理解しておくことが重要です。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産を所有していると、毎年かかるのが固定資産税です。この税は、不動産の価値に応じて課税され、一定の基準に基づいて算出されます。土地や建物を持っている限り納税義務があり、売却した場合にも関係するため、その仕組みを理解しておくことが大切です。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点の不動産所有者と決められています。そのため、売却したとしても、年度途中で所有者が変わる場合には、税の負担について事前に合意することが重要になります。
固定資産税は、自治体から送付される納税通知書に基づき、年に一度または分割で納付するのが一般的です。納付期限を過ぎると延滞金が発生するため、期日までに支払うことが求められます。
固定資産税の計算には、評価額が影響します。土地や建物の評価額は、各自治体の固定資産課税台帳に記載され、一定の周期で見直しが行われます。評価額が変わると税額も変動するため、売却前に最新の評価額を確認しておくと良いでしょう。
都市計画区域内では、固定資産税に加えて都市計画税が課されることがあります。これは、市街地整備のための税で、自治体によって課税の有無が異なります。売却時には、この税の扱いも整理することが必要です。
| 項目 | 説明 |
| 納税義務者 | 1月1日時点の所有者 |
| 納税通知 | 各自治体から通知書が送付される |
| 納付方法 | 一括または分割納付 |
| 延滞金 | 期限内に納付しない場合に発生 |
| 評価額 | 固定資産課税台帳に基づいて算出 |
| 都市計画税 | 該当地域のみ課税 |
固定資産税は不動産を所有する限り継続して発生するため、売却する際には、納税義務の整理が不可欠です。
不動産を売却した場合、固定資産税の負担について売主と買主の間で精算することが一般的です。なぜなら、税は1年分を所有者が先に納める仕組みになっており、売却後も売主が全額負担するのは不公平だからです。
固定資産税の精算方法には、主に日割り計算が用いられます。これは、売却した日を基準に、その日までの分を売主、それ以降を買主が負担する形です。一般的には、1月1日を起算日とするか、4月1日を起算日とする方法が採用されます。
精算しないという選択肢もありますが、その場合、売主が年度分の税を全額負担することになります。これは契約の自由の範囲ですが、後々のトラブルを避けるためにも、契約時に税の負担について明確に定めておくことが重要です。
売却後に固定資産税が還付されることは基本的にありません。納めた税額のうち、未経過分を買主に負担してもらう形で調整するのが一般的です。
不動産売買契約時には、税負担の分担方法について合意し、契約書に明記しておくと安心です。特に法人間の取引では、仕訳処理の方法も決めておくと、後の手続きがスムーズになります。
固定資産税は、不動産を所有している限り毎年課税される税金であり、自治体が課税額を決定します。計算の基準となるのは、毎年1月1日時点での所有者です。この時点で所有している人が、その年の税金を支払う義務を負うため、途中で売却しても納税義務は基本的に変わりません。しかし、売主と買主の間で税金の精算を行うことが一般的です。
固定資産税の算出方法は、自治体ごとに決められた評価額をもとに計算されます。土地や建物ごとに異なる税率が適用され、建物の種類や用途によっても税額が変わることがあります。評価額は数年ごとに見直され、不動産市場の動向や周辺環境の変化によって増減することがあります。
税率は固定資産評価額に一定の割合をかけて算出されます。多くの自治体では、基本となる税率が定められていますが、都市計画税が加わる場合もあります。都市計画税は、都市の開発やインフラ整備に使用されるもので、市街地にある不動産には追加で課税されることが一般的です。
固定資産税には軽減措置が適用される場合があります。特定の条件を満たした住宅や新築物件では、一部の税負担が軽減されることがあるため、売却前に適用条件を確認することが重要です。
固定資産税は、年単位で課税されるため、不動産売却時には税金の負担をどのように分担するかが重要になります。売主が1月1日時点での所有者として納税義務を負うため、買主との間で税額を日割り計算し、適正に分配するのが一般的です。
日割り計算の方法は、大きく分けて二つの方式があります。一つ目は、1月1日を基準日とする方法です。この方法では、1年を通して売主が税金を負担し、売却後の期間分を買主が負担する形で精算を行います。二つ目は、4月1日を基準日とする方法です。この方式では、自治体の会計年度の始まりに合わせて、税金の計算を行います。どちらの方法を採用するかは、売買契約の取り決めによります。
エリアによって、計算基準が異なることもあります。関東では1月1日基準が一般的ですが、関西では4月1日基準で計算されることが多い傾向にあります。そのため、地域の慣習や契約内容を確認することが重要です。
売買契約の際、固定資産税の精算は重要な手続きの一つです。売主と買主が納税負担を公平に分担するために、事前に税金精算の取り決めを契約書に記載する必要があります。
精算の基本ルールとして、売却時点で未納分の固定資産税を売主が支払い、買主は売却後の税負担分を売主に支払う形を取ることが一般的です。この際、契約書には「固定資産税精算条項」を設け、支払い方法や精算時期を明確に定めておくと安心です。
手続きに必要な書類としては、固定資産税納税通知書、固定資産税評価証明書、不動産売買契約書などがあります。これらの書類を基に、売主と買主が負担額を決定し、売買契約の締結時または引き渡し時に精算を行います。
役所への申請は特に不要ですが、固定資産税の納税証明を必要とする場合は、市区町村の窓口で取得できます。税務署や自治体のホームページでも、税額や計算方法を確認することができるため、事前にチェックしておくと良いでしょう。
不動産売買では、固定資産税の精算がトラブルの原因となることもあります。そのため、契約段階で納税義務を明確にし、精算の計算方法や手続きについて合意しておくことが重要です。
固定資産税精算金は、不動産の売買取引において売主と買主の間で清算する金額です。この精算金は、売買契約時に定められた条件に基づき、売主がすでに納付した固定資産税を買主が負担する形で調整されます。税務処理の観点から、精算金の取り扱いが売主と買主で異なるため、正確な理解が求められます。
固定資産税は毎年1月1日時点の不動産所有者に課される税金ですが、不動産の売却が行われた場合、その年の固定資産税を売主が全額負担するのではなく、引渡し後の期間分を買主が負担する仕組みです。つまり、固定資産税は日割りで精算され、買主が売主に対して一定額を支払う形となります。
精算金の計算方法には、土地と建物の按分が関わる場合があります。例えば、固定資産税が土地と建物の両方にかかる場合、売主と買主の負担を公平にするために、一定の割合で按分し、精算額を決定することがあります。
土地と建物の按分は、自治体が公表している固定資産税評価額を基に決められます。固定資産税評価額とは、自治体が課税の基準とする不動産の評価額であり、この評価額に基づいて税額が計算されます。そのため、精算金を算出する際には、土地と建物それぞれの評価額を確認し、税額を適切に分けることが重要です。
固定資産税精算金は、税務処理上、売主にとっては課税対象となる可能性があり、買主にとっては取得価額に含められるかどうかがポイントとなります。税務上の正しい取り扱いを理解しておくことが、適切な会計処理につながります。
固定資産税精算金の仕訳処理は、個人と法人で異なります。会計上の処理を正しく行うことで、税務調査時のトラブルを避けることができます。
個人と法人の違い 個人の場合、固定資産税精算金は譲渡所得の計算に影響を与える項目として扱われることが一般的です。一方、法人の場合は、売買契約時に精算金の取り扱いを明確にし、経理処理の中で適切に計上する必要があります。
売主と買主の処理方法の違い 売主側の会計処理では、精算金を収益として認識するケースがありますが、税務上は売却益として計上されるかどうかの確認が必要です。一方で、買主側では、不動産取得の一部とみなされ、資産計上することが一般的です。
実際の仕訳例を挙げると、売主が固定資産税精算金を受け取る場合、次のような処理になります。売主と買主の会計処理は異なり、それぞれの立場によって適切な方法を選ぶことが求められます。
固定資産税精算金が消費税の対象となるかどうかは、不動産取引における税務の大きなポイントです。一般的に、固定資産税は地方税であり、消費税の課税対象とはなりません。しかし、売買契約における精算金が消費税の対象となるかどうかは、取引の内容によります。
土地と建物の税務上の違い 土地部分の固定資産税精算金は、消費税がかかりません。一方、建物部分の固定資産税精算金については、消費税の対象となる場合があります。これは、建物が消費税の課税対象であるためです。
売主が課税事業者であり、かつ建物部分の精算金を請求する場合、請求額に消費税を含める必要があります。逆に、買主が課税事業者でない場合、仕入税額控除の対象とはなりません。
消費税が適用される場合 固定資産税精算金に消費税が適用されるのは、次のようなケースです。
税務処理の際には、売買契約の内容を確認し、適切に消費税の扱いを判断することが大切です。買主が支払う精算金に消費税が含まれる場合、売主側で適切な消費税計上を行う必要があります。
固定資産税精算金の取り扱いは、売主・買主の税務処理に影響を与えるため、適切な知識を持ち、契約書の内容を十分に理解しておくことが求められます。
固定資産税の特例制度は、一定の条件を満たす場合に適用される税の軽減措置です。不動産を所有する際に税負担を抑えるための重要な制度であり、適用できるケースを把握しておくことが大切です。
固定資産税の軽減措置
固定資産税の軽減措置は、土地や建物の種類、用途、所有者の条件などによって異なります。特に、住宅用地や新築住宅に対する軽減措置が代表的です。
申請方法と適用条件
固定資産税の軽減措置を受けるためには、一定の手続きが必要です。一般的には、申請書類を自治体に提出し、必要な条件を満たしていることを証明する書類を添付することになります。
申請に必要な主な書類は以下の通りです。
| 軽減措置の種類 | 必要書類 | 提出先 |
| 住宅用地の特例 | 住民票、登記簿謄本 | 市町村役場 |
| 新築住宅の軽減措置 | 建築確認通知書、固定資産評価証明書 | 市町村役場 |
| 耐震・省エネ改修 | 工事証明書、領収書 | 市町村役場 |
申請期限や具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
固定資産税の負担を軽減するためには、制度を活用するだけでなく、売却のタイミングや他の税制優遇措置との併用を考えることも重要です。
売却時期の調整による影響
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。そのため、売却のタイミングを考えることで、税の負担を軽減することが可能です。
例えば、1月1日を過ぎて売却した場合、その年の固定資産税の支払い義務は売主にあります。反対に、年末までに売却を完了すれば、翌年の固定資産税を支払う必要がなくなります。売却の時期を調整することで、税負担を軽減できる可能性があります。
他の税制優遇制度との併用
固定資産税以外にも、不動産売却に関する税制優遇制度がいくつかあります。例えば、特定の条件を満たせば譲渡所得税の控除を受けられる制度や、住宅ローン控除との併用も可能な場合があります。
主な税制優遇措置には以下のようなものがあります。
これらの制度を併用することで、固定資産税の負担を軽減できる可能性があるため、売却時には専門家に相談することが推奨されます。
固定資産税を抑えるだけでなく、不動産売却全体の税負担を軽減する方法も検討することが重要です。
固定資産税以外の税制優遇を活用する方法
不動産を売却する際には、固定資産税だけでなく、譲渡所得税や登録免許税などの負担も発生します。これらの税負担を軽減するために、利用できる税制優遇措置を確認することが大切です。
不動産を売却した際に適用される「居住用財産の3,000万円控除」や、「買換えの特例」などを活用すると、譲渡所得税の負担を軽減できる可能性があります。
長期保有している不動産であれば、税率が軽減されるケースもあります。一定の条件を満たせば、不動産売却にかかる税金が優遇されるため、売却前に確認しておくとよいでしょう。
専門家に相談するメリット
税制は非常に複雑で、適用できる制度を把握するのが難しいこともあります。固定資産税の節税や不動産売却の税負担を抑えるためには、税理士や不動産の専門家に相談することが有効です。
専門家に相談することで、以下のようなメリットがあります。
特に、不動産の売却額が大きい場合や、相続・贈与が絡むケースでは、事前に専門家と相談しながら進めることで、税負担を抑えながらスムーズに取引を進めることができます。
固定資産税の負担を抑えるためには、特例制度を活用するだけでなく、売却のタイミングや他の税制優遇制度を組み合わせることがポイントになります。適切な方法を選択し、税負担を最小限に抑えるための準備を進めましょう。
不動産を売却した後も、売主に対して固定資産税の支払い義務が生じる場合があります。固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されるため、売却のタイミングによっては売主が税金を負担し、買主と精算する必要があるのです。この点について詳しく解説していきます。
売却が完了しても、売主が固定資産税を納付するケースが存在します。固定資産税は1月1日時点の所有者に対して課税され、自治体から納税通知書が送付される仕組みです。一般的に、売買契約時に日割り計算を行い、売却日以降の負担分を買主に請求する形で精算が行われます。
ただし、以下のような状況では売却後も売主が納税義務を負う可能性があります。
これらのケースでは、売主が税金を支払った後に、必要に応じて買主へ精算を求めることになります。
固定資産税の納税通知書は、売主のもとへ1年に1回、自治体から送付されます。売却した後でも、納税義務者として通知が届くことがあるため、以下の点に注意しましょう。
これらの流れを適切に管理することで、売却後の固定資産税に関するトラブルを未然に防ぐことができます。
売却時に固定資産税を日割り計算し、売主と買主の間で負担を分けるためには、固定資産税精算書を作成することが重要です。この書類を正しく作成することで、税金に関する誤解やトラブルを防ぐことができます。
精算時に必要な書類
固定資産税精算を行う際に、以下の書類を準備するとスムーズです。
これらの書類を基に、精算内容を明確にしていきます。
清算書の作成フォーマットとポイント
固定資産税の精算書を作成する際には、以下の要素を明記すると分かりやすくなります。
| 項目 | 内容 |
| 物件情報 | 売却した不動産の所在地・登記情報など |
| 固定資産税額 | 当該年度の固定資産税総額 |
| 売却日 | 売却した日付(引き渡し日) |
| 売主負担額 | 売却日までの日数分の固定資産税額 |
| 買主負担額 | 売却日以降の日数分の固定資産税額 |
| 支払い方法 | 売主・買主間での精算方法(振込・現金など) |
作成時の注意点
固定資産税の精算は売主・買主双方にとって重要な手続きです。適切な書類を用意し、正確に精算を行うことで、売却後のトラブルを回避し、スムーズな取引を実現することができます。
固定資産税と都市計画税は、不動産を所有する際に課される税金ですが、それぞれの目的や適用範囲、計算方法が異なります。固定資産税は、土地や建物の所有者が負担する税金で、市町村が課税主体となります。一方、都市計画税は、都市計画区域内の土地や建物に対して課されるもので、都市開発のための財源として活用されます。
固定資産税の課税対象は、すべての土地や建物に及びます。これに対し、都市計画税の対象となるのは、都市計画区域内にある不動産に限定されているため、すべての不動産に適用されるわけではありません。
税額の計算方法にも違いがあります。固定資産税は、固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されます。都市計画税も同様に固定資産税評価額を基に計算されますが、適用される税率が異なります。市町村ごとに都市計画税の税率は異なり、税負担が自治体によって差が出ることがあります。
税の使途にも違いがあります。固定資産税は地方自治体の一般財源として使われるのに対し、都市計画税は都市開発や道路整備、公園整備といった特定の目的のために使用されます。固定資産税と都市計画税には適用範囲や税額の決まり方に違いがあるため、所有する不動産がどのような課税対象になるのかを確認しておくことが重要です。
固定資産税と都市計画税の計算方法は基本的に似ていますが、税率や負担割合に違いがあります。固定資産税は、固定資産税評価額に一定の税率を掛けて算出されます。都市計画税も同じ評価額を基準に算出されますが、税率が固定資産税とは異なります。
固定資産税の負担割合は、所有者が100%負担することが一般的ですが、都市計画税は特定の都市計画区域内に限定されるため、適用される地域とされない地域があります。自治体によっては都市計画税の軽減措置が設けられることもあり、都市計画税が課されないケースもあります。
不動産を売却する際の税精算についても注意が必要です。売却時には固定資産税と都市計画税の負担割合を調整する必要があります。例えば、売主と買主の間で、固定資産税および都市計画税を日割りで精算するのが一般的です。この際、どちらがどの程度負担するのかを事前に取り決めておくことが重要になります。
売却後に都市計画税がどのように処理されるのかについても確認しておくべきです。売却時の契約内容によっては、売主が一定期間の税金を負担し、その後買主が支払う形になることがあります。これにより、固定資産税および都市計画税の支払い負担が不動産取引の際に生じるため、事前に契約書をよく確認しておくことが重要です。
都市計画税の納税方法には自治体ごとの違いがあるため、管轄する自治体に確認することが求められます。特に都市計画税の支払いを忘れると延滞金が発生する可能性があるため、売却後の税負担についてもしっかり把握しておく必要があります。
以下のような表を参考にすると、固定資産税と都市計画税の違いがより分かりやすくなります。
| 項目 | 固定資産税 | 都市計画税 |
| 課税主体 | 市町村 | 市町村 |
| 課税対象 | すべての土地・建物 | 都市計画区域内の土地・建物 |
| 税率 | 固定税率 | 市町村によって異なる |
| 使途 | 一般財源 | 都市開発・道路整備 |
| 売却時の精算方法 | 売主・買主間で日割り計算 | 固定資産税と同様の精算方法 |
固定資産税と都市計画税は似ているようで異なる部分が多く、それぞれの税の仕組みを理解することが重要になります。不動産の売却や購入を考えている場合は、これらの税金がどのように計算されるのかを事前に把握し、契約時に適切に取り決めることが必要です。
不動産売却における固定資産税の精算は、売主・買主の双方にとって重要な手続きです。固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、売却時期によって負担の割合が変わります。日割り計算を誤ると、余計な支払いが発生する可能性があるため、契約時に明確にしておくことが必要です。
精算金は税務処理上、売主・買主それぞれの立場で適切な仕訳が求められます。法人と個人では経理処理の方法が異なり、買主側では固定資産の取得価額に含めるケースもあります。税務上の取り扱いを誤ると、後に修正申告が必要になることもあるため、事前に確認しておくことが重要です。
売却後の手続きも忘れてはいけません。固定資産税の納付は売却年度の6月頃に行われますが、売却後も納税通知書が送付される場合があります。売却済みの不動産に対する誤納付を防ぐためにも、自治体へ所有権移転の届け出を行い、固定資産税の納付先を明確にしておくことが推奨されます。
不動産売却時の固定資産税について正しく理解し、適切な精算・申告を行うことで、トラブルを防ぎ、スムーズな取引を実現できます。税額計算の方法や契約書への記載事項を事前に把握し、専門家に相談することで、安心して不動産売却を進めることができるでしょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
Q. 不動産売却時に固定資産税はどのように精算されますか?
A. 固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されるため、売却時には日割り計算で売主・買主間で負担を調整します。例えば、4月1日に売却した場合、売主は1月1日から3月31日までの期間分を負担し、それ以降は買主の負担となります。ただし、売買契約によって異なるため、契約書に記載された精算方法を確認することが重要です。
Q. 固定資産税精算金は消費税の対象になりますか?
A. 土地にかかる固定資産税精算金は非課税ですが、建物に関しては消費税の課税対象となる場合があります。例えば、土地3,000万円・建物1,000万円の不動産を売却し、固定資産税の精算額が10万円だった場合、そのうち建物部分の割合に応じた精算金が消費税の対象になります。契約時に「固定資産税精算金の消費税処理」について確認し、適切に計上することが求められます。
Q. 固定資産税の納税通知書は売却後も届くことがありますか?
A. はい、売却後も1月1日時点の所有者宛に納税通知書が届くことがあります。例えば、6月に固定資産税の通知書が送られた場合、すでに売却済みであっても売主の元に届く可能性があります。納税義務の所在を明確にし、必要に応じて買主へ通知書を転送するか、自治体へ所有権移転の手続きを行いましょう。
Q. 固定資産税を節税する方法はありますか?
A. 一定の要件を満たすと固定資産税の軽減措置が適用される場合があります。例えば、新築住宅や耐震改修を行った住宅では軽減措置が受けられることがあり、条件によっては3年間税額が減額されることもあります。また、不動産売却のタイミングを調整し、税負担の少ない時期に取引を行うことで、支払う税額を抑えることが可能です。事前に自治体の制度を確認し、適用できる軽減措置を活用することが大切です。
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。