東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年10月3日
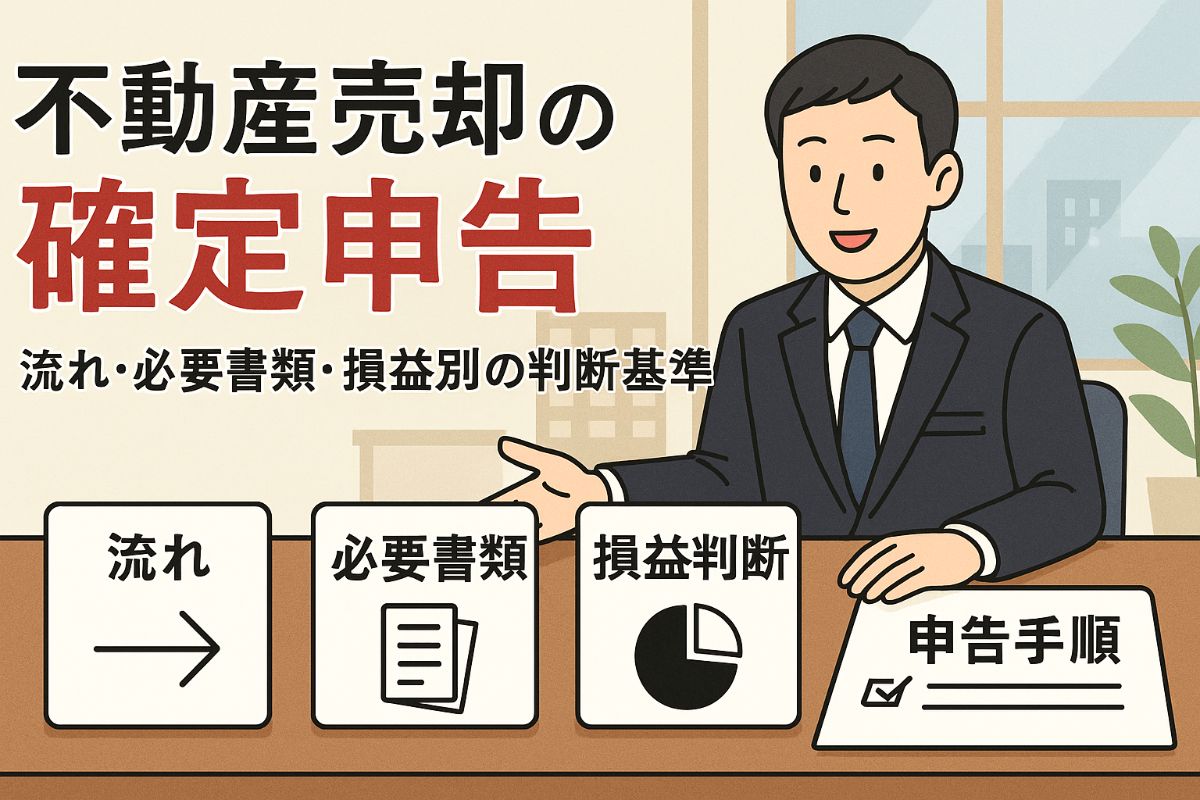
不動産を売却した後、「確定申告が必要なのか?」「どんな書類を揃えればいいのか?」と悩んでいませんか。売却によって【譲渡所得】が発生した場合、ほとんどのケースで申告義務がありますが、損失が出た場合や特例の適用によって不要となる場合も存在します。特に【マイホームの特別控除】や相続不動産の特例などは、条件を満たせば大きな節税につながる反面、申告漏れによる追徴課税や延滞税のリスクも決して少なくありません。
税制改正や申告期限、必要書類の変更など、毎年のようにルールが更新されているため、「昨年と同じ」と思い込むのは危険です。実際に、書類不備や計算ミスによる追加徴税の事例も増加傾向にあります。
この記事では、不動産売却後の確定申告が「必要」か「不要」かの判断基準から、申告手続きの流れ、正しい書類準備・計算方法、失敗しないための注意点まで、詳しく解説します。
「損失申告を放置して数十万円の控除を逃した」「期限を過ぎて延滞税が発生した」といった失敗を未然に防ぎたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却を行った場合、必ずしも確定申告が必要とは限りません。判断のポイントは「譲渡所得」が発生しているかどうかです。譲渡所得とは、不動産の売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いた利益のことで、この金額がプラスの場合は原則として確定申告が必要です。利益が出ていない場合や特例が適用される場合には、申告義務がないケースもあります。不動産売却の確定申告の仕方や必要書類、売却時のコツなどを事前に確認し、状況に応じて正しく対応しましょう。
確定申告が不要となる場合は主に以下のケースです。
不動産売却による所得が一定基準に満たないときや、譲渡所得の金額がゼロまたはマイナスの場合は申告が不要となることがあります。特に、「譲渡所得50万円以下 申告不要」や「譲渡所得 申告不要」というワードで検索されることが多く、実際に売却金額より取得費や譲渡費用が大きい場合は該当します。
不動産売却で損失が出た場合、原則として確定申告は不要です。ただし、損益通算や繰越控除を利用したい場合は申告が必要になるため注意が必要です。損失が発生した場合でも、申告しないことで控除や税制優遇を受けられなくなる可能性があります。
確定申告が不要な場合でも、控除や損益通算の観点から申告を検討すべきケースがあります。例えば、マイホームの譲渡損失は他の所得と損益通算できる場合があり、申告を行うことで翌年以降の税金を軽減できることがあります。控除や損益通算をしないと、本来受けられる節税メリットを逃す点を理解しておきましょう。
譲渡所得が発生した場合、または特例(特別控除など)を利用する場合は確定申告が必要です。特に、以下のケースで申告が求められます。
| ケース | 申告の必要性 | ポイント |
|---|---|---|
| 利益が出た場合 | 必要 | 譲渡所得の計算が必須 |
| 特別控除を使う場合 | 必要 | 控除適用には申告が条件 |
| 損失の損益通算・繰越控除を使う場合 | 必要 | 節税効果を得るために申告 |
申告を怠ると税務署から指摘を受けたり、本来受けられる特例が適用されないこともあるため、利益発生時や特例利用時の申告は忘れずに行いましょう。
不動産の種類や譲渡理由によって、申告義務や必要書類が異なります。
損失が発生した場合でも、確定申告を行うことで損益通算や繰越控除を活用できます。
損益通算や控除の活用は税額の軽減につながるため、損失が出た場合も確定申告を積極的に検討しましょう。必要書類や申告方法は国税庁のサイトや専門家への相談も有効です。
不動産売却後の確定申告は、譲渡所得の有無にかかわらず正しい手順を踏むことが重要です。売却益が出た場合は原則申告が必要となり、特例や控除の適用で納税額が大きく変わるため、流れを把握しておくと安心です。
不動産売却時の確定申告の流れ
申告期間は翌年の2月16日から3月15日までが一般的です。事前準備をしっかり行い、余裕を持って手続きすることがトラブル防止のコツです。
不動産売却の確定申告は、自分で行う場合も正確な書類準備と順序がポイントです。まず、売却した不動産の取得費や譲渡費用を計算し、譲渡所得を算出します。売却に関する契約書や領収書、登記事項証明書などは必ず保管しましょう。また、土地・建物の取得時や売却時の費用も記録しておくと、正しい計算につながります。
確定申告書は国税庁のホームページで作成できます。e-Taxを使えば自宅から申告可能で、添付書類も電子化できます。税務署窓口や郵送でも受け付けていますが、期限に遅れないよう注意が必要です。
確定申告時に必要な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 主な入手先・備考 |
|---|---|
| 確定申告書B | 税務署・国税庁サイト |
| 譲渡所得の内訳書 | 税務署・国税庁サイト |
| 売買契約書の写し | 手元保管・不動産会社 |
| 登記事項証明書 | 法務局 |
| 取得時の契約書の写し | 手元保管・不動産会社 |
| 仲介手数料等の領収書 | 不動産会社 |
| 本人確認書類(免許証等) | 自身で用意 |
書類は早めに揃えることで、申告作業がスムーズに進みます。
提出方法は大きく3つに分かれます。
それぞれ期限を厳守し、添付漏れや記入ミスに注意しましょう。
居住用財産の特別控除を利用する場合、追加の書類が必要です。
| 追加書類名 | 用途・備考 |
|---|---|
| 戸籍の附票の写し | 住所履歴の証明 |
| 住民票の除票または写し | 売却物件が居住用であった証明 |
| 家屋・土地の登記事項証明書 | 所有期間・居住歴の確認 |
これらは市区町村役場や法務局で入手できます。控除条件をよく確認し、必要書類をもれなく用意してください。
登記事項証明書は法務局で取得できます。申請時には不動産の所在地や地番、家屋番号が必要です。オンライン申請も可能で、手数料は窓口より安価な場合があります。
証明書には所有者の履歴や登記内容が記載されています。申告時は、売却した不動産の情報が正しいかを必ず確認してください。
申告書作成時のミスとして多いのは、取得費や譲渡費用の記載漏れ、添付書類の不足、計算ミスです。
しっかりと内容を確認しながら進めることで、トラブルや追加提出のリスクを減らせます。
不動産売却を行うと、譲渡所得に対して所得税・住民税が課税されます。譲渡所得とは、売却によって得た利益を指し、取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。正確な税金計算と確定申告を行うためには、売却金額・取得費・譲渡費用の把握が不可欠です。特例や控除の利用可否もあわせて確認しましょう。税率や控除条件を誤ると納税額が変わるため、国税庁のガイドラインや専門家の情報を参照し、確実な申告を心掛けてください。
譲渡所得の計算方法は以下の通りです。
譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費には購入代金や仲介手数料、登記費用が含まれます。建物の場合は減価償却費を差し引く必要があります。譲渡費用には売却時の仲介手数料、印紙税、測量費などが該当します。下記のテーブルで主な項目を整理します。
| 項目 | 説明例 |
|---|---|
| 取得費 | 購入代金、仲介手数料、登記費用など |
| 減価償却費 | 建物の場合、経過年数分を差し引く |
| 譲渡費用 | 売却仲介手数料、印紙税、測量費など |
計算方法や書類の保存状況によっては、金額が変動するため注意が必要です。
土地売却時の確定申告では、まず譲渡所得を計算します。次の手順で進めるとスムーズです。
売却代金が約2,000万円、取得費が約1,500万円、譲渡費用100万円前後の場合、譲渡所得は2,000−(1,500+100)=400万円前後です。必要事項を記入し、申告期間中に提出しましょう。
不動産の所有期間により適用される税率が異なります。
| 所有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 5年超(長期譲渡) | 約20% |
| 5年以下(短期譲渡) | 約39% |
長期譲渡所得では税率が低くなり、節税につながります。所有日数は売買契約日ではなく取得日から売却日までで判断します。所有期間の確認は登記事項証明書などで正確に行いましょう。
不動産売却に伴う確定申告は、特例の適用や相続物件、共有名義、損失申告など、複雑なケースも少なくありません。計算や書類作成に不安がある場合は、税理士への相談が有効です。税理士費用の相場は5万円〜15万円程度が一般的ですが、内容や地域、物件の状況により異なります。正確な申告や節税対策のためにも、費用対効果を考慮して専門家の助言を活用しましょう。
税理士に相談することで、譲渡所得の計算ミスや書類不備を防げます。また、特例や控除の適用漏れを防ぎ、最大限の節税が期待できます。依頼時は実績や報酬体系を事前に確認し、見積書を取りましょう。以下のポイントを押さえておくことが重要です。
信頼できる税理士を選ぶことで、安心して確定申告を進めることができます。
不動産売却の譲渡所得に対する確定申告では、特例や控除を適切に利用することで税負担を大きく減らすことが可能です。主な節税手法には、居住用財産の特別控除、10年超所有による軽減税率、そして譲渡損失の損益通算・繰越控除があります。これらを活用することで、税額の大幅な軽減や、将来の税負担の調整が期待できます。
特別控除の主な利用条件
申告時の注意点
軽減税率が適用される条件
具体的な税率比較表
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
|---|---|---|
| 5年以下 | 約30% | 約9% |
| 5年超10年以下 | 約15% | 約5% |
| 10年超(6,000万円以下部分) | 約10% | 約4% |
| 10年超(6,000万円超部分) | 約15% | 約5% |
不動産売却で損失が出た場合、損益通算や繰越控除の特例を活用することで他の所得と相殺が可能です。
申告方法のポイント
損益通算・繰越控除の活用例
不動産売却において特例や控除を最大限利用するには、売却時期・必要書類の準備・適切な申告手続きが重要です。
申告書作成時の重要ポイント
よくあるミスと対策
特例や控除の条件は複雑な場合も多いため、事前準備と丁寧な確認が節税のカギとなります。
不動産売却時の確定申告を自分で行う際は、流れをしっかり把握することが重要です。まず、譲渡所得の計算から始めます。取得費や譲渡費用を正確に算出し、課税対象となる所得金額を導きます。続いて必要書類を準備し、申告書類を作成します。書類の記入が完了したら、税務署への提出、もしくはe-Taxを利用したオンライン提出を選択します。これらの手順を踏むことで、確定申告を自力で完結させることが可能です。
主なステップ一覧
e-Taxはスマートフォンからも利用可能で、申告書作成コーナーが非常に便利です。まず、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」にアクセスし、案内に従って不動産売却に関する情報を入力します。スマホのカメラで必要書類を撮影し、画像データとして添付できるため、書類提出もスムーズです。
スマホ申告のポイント
e-Taxでの提出時には、譲渡所得に関わる添付書類の準備が必須です。具体的には、売買契約書、登記事項証明書、取得費証明などが求められます。書類はPDFや画像ファイルに変換し、指定されたフォーマットでアップロードします。ファイルサイズや形式のエラーには事前に注意が必要です。
主な添付書類一覧
| 書類名 | 入手先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 売買契約書 | 仲介業者等 | 両面を撮影、全ページ必須 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 最新のものを用意 |
| 取得費証明(領収書等) | 売主が保管 | 不足時は説明書を作成 |
トラブル回避策
確定申告の提出方法には、オンライン(e-Tax)と紙による税務署窓口・郵送の2つがあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選択しましょう。
提出方法比較表
| 提出方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| e-Tax | 自宅で完結、24時間提出可能 | 初回はマイナンバーカード等の準備が必要 |
| 紙(窓口・郵送) | 直接相談しながら提出できる | 書類不備時の修正に手間がかかる |
オンライン提出は利便性が高く、スマホやパソコン操作に慣れている方に適しています。一方、紙提出は対面で質問できる安心感があります。
譲渡所得の確定申告時は、最新のチェックリストを活用して添付書類の漏れを防ぎましょう。国税庁が公開しているチェックリストは、必要書類を一目で確認できるため、準備漏れによるトラブル防止に役立ちます。
チェックリスト活用の流れ
強調ポイントとして、全ての書類が揃っているか最終確認を怠らないことがスムーズな申告のコツです。
不動産売却に伴う確定申告を税理士へ依頼する場合、費用相場は一般的に5万円〜15万円程度が目安です。売却価格や物件の種類、申告内容の複雑さによって費用は変動します。特別控除や譲渡損失の申告が絡む場合は、追加料金が発生するケースもあります。依頼するタイミングは、売買契約締結後〜翌年の確定申告開始前までが理想です。早めに相談することで、必要書類の準備や節税対策を万全に整えることができます。
税理士費用の目安
| 項目 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本報酬 | 5万円〜10万円 | 単純な売却の場合 |
| 特例・控除対応 | 2万円〜5万円 | 特別控除・損失申告等 |
| 追加書類作成・調査対応 | 1万円〜3万円 | 書類紛失・複雑案件 |
適切なタイミングで税理士に依頼することで、税務署からの指摘や申告漏れのリスクを回避しやすくなります。
税理士報酬には、主に「定額制」「成果報酬型」「作業別加算型」があります。定額制は内容が明確で安心ですが、追加作業発生時は別途費用が必要になることもあるため、契約前の見積もり確認が必須です。成果報酬型は、節税金額や還付額に連動して報酬が変動する仕組みで、節税メリットが大きい場合に適しています。一方、作業別加算型は書類作成や調査ごとに細かく費用が設定されるため、作業内容や請求項目を事前に把握しておくことが重要です。
料金形態別の特徴一覧
| 料金形態 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 定額制 | 安心感が高く、予算管理しやすい | 追加作業が発生すると割高になる場合あり |
| 成果報酬型 | 節税額や還付金に応じて報酬が変動 | 節税効果が小さい場合は割高になることも |
| 作業別加算型 | 必要なサービスのみ依頼可能 | 全体費用が不明瞭になるケースがある |
契約内容と見積もりの明細をしっかり確認し、不明点は事前に質問しておくことが大切です。
不動産売却時の確定申告に強い税理士を選ぶには、以下のポイントが重要です。
不動産売却の確定申告は専門的な知識が求められるため、実績豊富な税理士を選ぶことで安心して任せられます。
自分で不動産売却の確定申告を行う場合、税理士費用は不要ですが、申告内容の誤りによる追徴課税や控除漏れのリスクが高まります。国税庁のホームページやe-Taxを利用すれば、ある程度は自己完結できますが、複雑な特例適用や複数物件の処理には専門知識が不可欠です。費用対効果を考える際は、以下の比較ポイントを参考にしてください。
自分で行う場合も、必要書類や申告方法を事前にしっかり確認し、疑問点は税務署に相談することが大切です。
| ケース | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 売却金額が大きい・特例適用が必要な場合 | 節税対策や複雑な申告もプロが対応し安心 | 費用が発生する |
| 売却物件が1件のみ、内容がシンプルな場合 | 費用を掛けずに済む、自分のペースで進められる | 申告ミスや控除漏れのリスクがある |
| 複数の不動産や相続物件の売却が絡む場合 | 複雑な計算や添付書類の用意も任せられる | 費用が高くなることがある |
自分の状況や売却内容に合わせて、税理士依頼の必要性を検討することが賢明です。正確な申告はトラブル防止や将来の資産管理にもつながります。
不動産売却時の確定申告は、申告期限を過ぎると重い罰則や延滞税が課せられることがあります。特に売却益が出た場合、翌年2月16日から3月15日までの間に必ず申告が必要です。申告期限を逃すと、以下のリスクが発生します。
普段確定申告が不要な方でも、不動産売却の際には特に注意が必要です。
書類の不備や記入ミスは、追加徴税や申告やり直しの原因となります。具体的な不備例を以下の表でまとめます。
| 不備内容 | 主な影響 | 主な対策 |
|---|---|---|
| 売買契約書の添付漏れ | 申告内容が認められない | 添付書類リストで確認 |
| 取得費の証明不足 | 譲渡所得の計算額が不正確 | 領収書・登記事項証明書を準備 |
| 記入欄の誤記 | 税額計算ミス・差額納付の可能性 | 記入例や国税庁サイトで確認 |
特に売買契約書や登記事項証明書などの原本は、事前にコピーを取り、提出前に再度確認しましょう。
万が一、必要書類を紛失した場合は、速やかに再取得の手続きを行うことが重要です。主な再取得方法は以下の通りです。
| 書類名 | 再取得先 | 注意点 |
|---|---|---|
| 売買契約書 | 不動産会社 | 再発行に日数がかかる場合あり |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 交付手数料が必要 |
| 住民票・戸籍附票 | 市区町村役場 | 本人確認書類が必要 |
再取得には時間がかかることが多いため、早めの手続きがポイントです。
譲渡所得や税額の計算ミス、記入欄の転記ミスを防ぐためには、以下の対策が有効です。
特に譲渡所得計算時は、取得費や譲渡費用の控除漏れがないか確認しましょう。スマホでもe-Taxによる申告が可能です。
確定申告の失敗を防ぐために、チェックリストを活用しましょう。
| チェック項目 | よくあるミス |
|---|---|
| 必要書類が全て揃っているか | 添付書類の不足 |
| 申告内容に誤りがないか | 記入漏れや誤記入 |
| 特別控除や特例の適用条件を満たしているか | 控除条件の誤認 |
| 税額計算が正確か | 計算式や控除額の計算ミス |
| 提出期限を守っているか | 期限後の申告・納税 |
初めて自分で申告する場合は、税務署や税理士への相談も有効です。
不動産売却時の確定申告は、申告期間や税制改正のポイントを正確に把握することが重要です。不動産売買による譲渡所得が発生した場合、原則として翌年の2月16日から3月15日までに申告を行う必要があります。令和6年分の確定申告では、スマートフォンやe-taxを使った申告方法がより普及し、添付書類の電子化が進んでいます。特にマイホーム売却による「特別控除」などの特例を適用する場合、適用条件や提出期限をしっかり確認しましょう。
下記のテーブルは、申告に必要な主なポイントをまとめたものです。
| 内容 | 最新情報 |
|---|---|
| 申告期間 | 毎年2月16日~3月15日 |
| 主な税制改正点 | 添付書類の簡素化、e-tax申告の利便性向上 |
| 特例適用の条件 | 居住用財産・譲渡所得・所有期間・同一生計条件等 |
| 申告不要なケース | 譲渡損失や50万円以下、特定要件を満たす場合 |
不動産売却の確定申告では、成功事例・失敗事例の両方から学ぶことが大切です。譲渡所得の申告不要と誤解し申告を怠った場合、後日追徴課税などのリスクが高まります。一方、必要書類を揃え、特例や控除を正しく活用できたケースでは、税負担を大幅に軽減できています。
たとえば、マイホーム売却時に「所有期間や居住要件を満たすか」を事前確認したことで、控除が適用された事例があります。逆に、領収書の紛失や取得費の証明不足で控除額が減額された例も見られます。
| 事例 | ポイント |
|---|---|
| 成功事例 | 書類を早めに準備、特例要件を事前確認し適用 |
| 失敗事例 | 書類紛失、申告忘れ、取得費証明不備 |
不動産売却時の確定申告で重要なのは、次のような点です。
これらを徹底することで、申告ミスや控除漏れを防ぎ、安心して不動産売却の確定申告を完了できます。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。