東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年11月3日
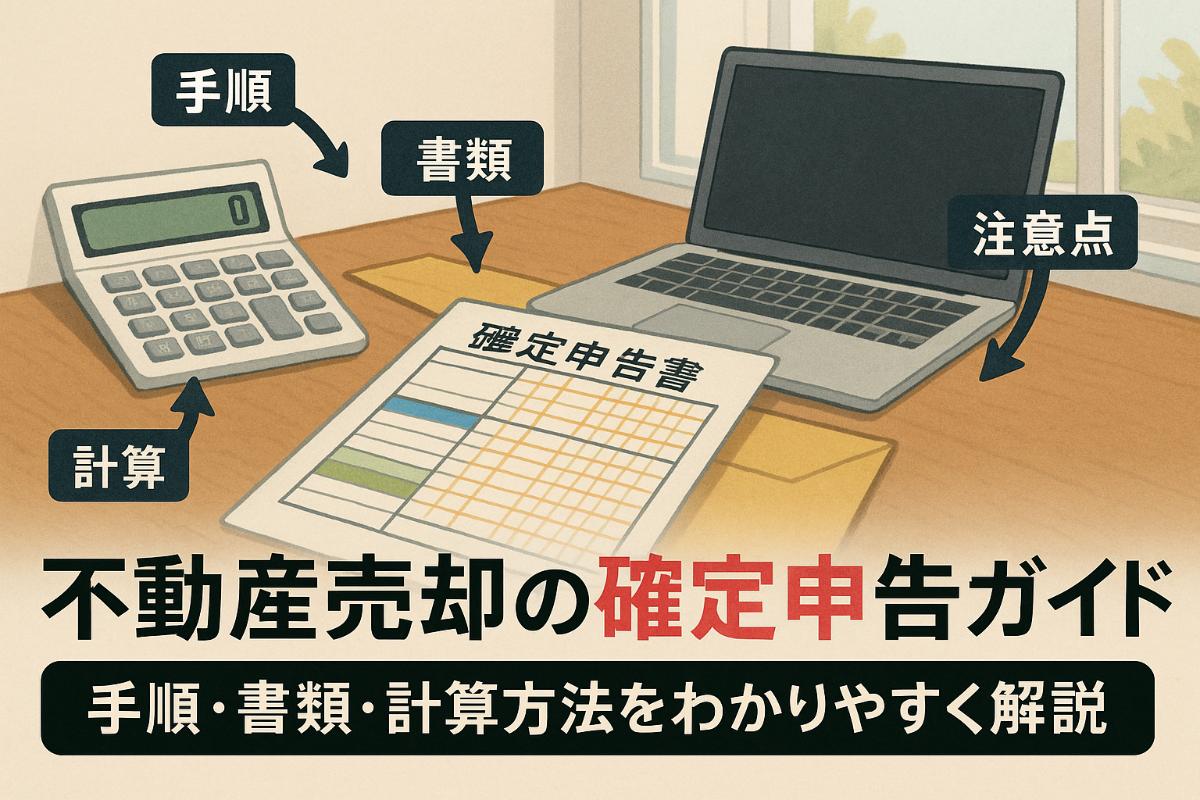
不動産を売却した後、「確定申告は本当に必要なの?」「手続きや申告書の書き方が分からず不安…」と感じていませんか。
実際に、【2022年の国税庁統計】では不動産売却に関連する申告件数は年々増加傾向にあり、特に個人による譲渡所得の計上ミスや必要書類の不備による指摘事例も多発しています。こうした背景から、申告不要と判断してしまい後で追徴課税を受けるケースも少なくありません。
特に、不動産の譲渡所得が50万円以下の場合や、3,000万円の特別控除を適用できるかどうかなど、「どのケースで申告が必要なのか」「自分はどんな書類を準備すればいいのか」といった悩みは多くの方が直面するポイントです。正しい知識と具体的なやり方を知っておくことで、余計な税金や損失を回避できます。
このページでは、不動産売却後の確定申告の必要性や手順、よくある注意点まで徹底解説。初めての方でも分かりやすいよう、【申告方法の全体像・必要書類一覧・特例利用時の注意点・具体的な記入例】まで網羅しました。
最後まで読むことで、自分に必要な手続きが明確になり、安心して確定申告を進められる具体的な方法が手に入ります。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産を売却した場合、原則として所得税や住民税の対象となる譲渡所得が発生します。譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた金額で計算されます。特に不動産売買の際は、売却益が出たかどうかを正確に把握し、必要に応じて確定申告を行うことが重要です。近年はe-Taxを活用して自宅から申告ができるため、手続き面もスムーズになっています。
下記の表は、不動産売却に関わる主な税金や確定申告の必要性の有無をまとめたものです。
| 売却パターン | 確定申告の必要性 | 主な注意点 |
| 譲渡所得が発生した場合 | 必要 | 必要書類を揃え期限内に申告 |
| 譲渡損失が発生した場合 | 条件による | 損失の繰越控除など特例を活用 |
| 50万円以下の所得のみ | 不要(条件あり) | 条件を満たせば不要 |
| 相続・贈与による売却 | 必要(原則) | 特例や控除の適用を検討 |
不動産売却でも確定申告が不要なケースがあります。まず、譲渡所得が50万円以下の場合や、譲渡損失が発生し控除等を適用しない場合です。また、相続や贈与による売却でも、一定額以下で他の所得と合算しても課税されない場合は申告が不要となります。ただし、各種特例や控除を受ける場合には申告が必要なので注意が必要です。
申告不要の主な条件
ただし、少額でも税務署から連絡が来るケースや、後日修正申告が必要になることもあるため、慎重に判断しましょう。
不動産売却時の確定申告が必要となる最大の理由は、譲渡所得が発生した場合です。譲渡所得は、売却価格から取得費・譲渡費用を差し引いて計算され、課税対象となります。税務署は売買契約書や登記情報をもとにチェックしており、申告漏れには厳しく対応します。
税務上の主なチェックポイント
正しい金額での計算や書類の保存が求められ、税務調査の対象となることもあるため、事前に準備を整えておくことが重要です。
不動産売却に伴う確定申告は、以下の手順で進めるとスムーズです。特にe-Taxを利用すれば、書類提出もオンラインで完結します。初心者でも分かりやすい流れを紹介します。
申告手順の全体像
主な必要書類一覧
| 書類名 | 用途 |
| 売買契約書 | 売却価格の証明 |
| 登記事項証明書 | 所有者・物件情報の証明 |
| 譲渡所得の内訳書 | 所得計算・内訳の記載 |
| 取得費/譲渡費用の領収書等 | 経費計上の証明 |
| 3,000万円控除等の適用書類 | 特例申請時に必要 |
正確な申告と書類の整備で、税金トラブルを未然に防ぎましょう。
不動産売却後の確定申告では、正確な書類準備が不可欠です。必要書類を早めに揃えることで手続きがスムーズに進み、特例や控除の活用もしやすくなります。不動産売買の内容や適用する特例によって、求められる書類は変わるため、詳細を確認しながら進めることが重要です。
確定申告に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 詳細・用途 |
| 登記簿謄本(登記事項証明書) | 不動産の所有状況・売却物件の証明 |
| 売買契約書 | 売却価格・取引内容の証明 |
| 譲渡所得の内訳書 | 譲渡益等の申告に必要 |
| 取得費・譲渡費用の領収書 | 経費計上・譲渡所得計算に使用 |
| マイナンバー関連書類 | 個人番号確認に必須 |
| 確定申告書B・第三表 | 譲渡所得申告専用の税務書式 |
| 印鑑 | 書類提出時に必要な場合あり |
これらの他、仲介手数料やリフォーム費用など経費に該当する支払いの領収書も重要です。物件購入時の契約書、固定資産税納付書なども取得費や経費の証明として活用できます。
各種書類の入手や保管には注意が必要です。
申告時に必要な書類が不足すると再取得に時間がかかるため、売却前後は特に慎重に管理しましょう。
特例や控除を利用する場合は追加書類が必要です。
| 特例名 | 追加で必要な書類例 |
| 3,000万円特別控除 | 売却物件が居住用であることを示す住民票、戸籍附票など |
| 相続税取得費加算の特例 | 相続税の申告書、相続税納付書、遺産分割協議書など |
| 買換え特例 | 新たに購入した不動産の売買契約書や登記事項証明書 |
これらの書類は物件の用途や取得経緯、相続の有無などにより異なります。特例を確実に適用するには、各証明書の原本やコピーを用意し、内容が漏れなく記載されているかを確認しましょう。書類の不備や不足で特例が認められないケースもあるため、事前のチェックが大切です。
不動産売却後の確定申告では、まず譲渡所得の有無を判断し、必要に応じて書類を準備します。売却益が出た場合や特例を利用する際は、申告が必須です。以下の手順を参考に進めることで、ミスなくスムーズな申告が可能となります。
主な手順一覧
| 手順 | 内容 |
| 1 | 必要書類の準備(契約書、登記事項証明書など) |
| 2 | 譲渡所得の計算(取得費・譲渡費用の控除) |
| 3 | 確定申告書および譲渡所得内訳書の作成 |
| 4 | e-Taxや税務署窓口での提出 |
| 5 | 納税または還付手続き |
ポイント
確定申告書類では、正確な情報の記載が求められます。特に譲渡所得の内訳書は、取得時と売却時の金額、取得費、譲渡費用、特例適用の有無など、細かな情報を正確に記載する必要があります。
記入時の注意点リスト
よくあるミスと防止策
| ミス例 | 防止策 |
| 金額の記載漏れ | チェックリストを活用し、記入後に再確認 |
| 添付書類の不足 | 提出前に必要書類一覧で確認 |
| 控除欄の記載漏れ | 特例適用欄を必ずチェック |
e-Taxを利用すれば、自宅やスマートフォンからオンラインで確定申告が可能です。特にマイナンバーカードやICカードリーダーがあれば、本人確認もスムーズに行えます。スマホ申告にも対応しており、書類提出の手間を大幅に減らせます。
e-Tax申告のコツ
添付書類の管理
不動産売却に関する確定申告は、原則として売却した翌年の2月16日から3月15日までが期限です。申告場所は、納税地の税務署、またはe-Taxによるオンライン申告が利用できます。
重要ポイント
申告場所の選択肢
| 方法 | 特徴 |
| 税務署窓口 | 直接相談しながら提出可能 |
| 郵送 | 遠方でも利用しやすい |
| e-Tax | 24時間申告可能・自宅で完結 |
期限切れ時の対応策
この流れを押さえ、正しい情報と書類で不動産売却の確定申告を進めてください。
譲渡所得は不動産売却時に発生する所得で、以下の計算式で求めます。
| 項目 | 内容 |
| 譲渡所得 | 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)-特別控除 |
譲渡価額は実際の売却金額です。取得費は購入時の金額や購入時の諸経費(仲介手数料や登記費用など)を含みます。譲渡費用は売却にかかった仲介手数料や印紙税などです。特別控除は条件を満たせば最大3,000万円が適用されます。
必要情報の例
正確な計算には、これらの書類を事前に揃えておくことが重要です。
取得費・譲渡費用の意味や計算方法を具体例付きで説明
取得費は不動産購入時の金額に加え、登記や仲介手数料、リフォーム費用なども含まれます。例えば、購入価格2,000万円+仲介手数料60万円+登記費用20万円であれば、取得費は2,080万円です。
譲渡費用は売却時の仲介手数料や測量費、契約書の印紙税などが対象です。例えば、売却時の仲介手数料が80万円、印紙税が3万円なら、譲渡費用は83万円となります。
これらの費用は、証拠書類をもとに正確に積算しましょう。
不動産売却時には特別控除の活用が可能です。特に、居住用財産の場合は最大3,000万円の特別控除が適用されます。控除を受けるには、売却が自宅であることや過去2年間に同じ控除を受けていないことなどの条件があります。
取得費を計算する際、建物については経過年数に応じた減価償却費を差し引きます。例えば、木造住宅は22年で償却するため、築年数を考慮して取得費から減価償却費を控除します。
| 建物の種類 | 償却年数 | 償却率 |
| 木造 | 22年 | 0.046 |
| 鉄筋コンクリ | 47年 | 0.022 |
減価償却の計算式: 建物取得費 × 償却率 × 経過年数
費用や経費の積み上げは、領収書や契約書で裏付けることが大切です。
減価償却費や必要経費の具体的積み上げ方を明示
減価償却費は建物の取得費に経過年数と償却率をかけて算出します。例えば、取得費1,000万円の木造住宅を10年所有した場合、1,000万円×0.046×10年=460万円が減価償却費となり、取得費から差し引きます。
必要経費は以下の項目が該当します。
これらは証拠資料を保管し、確定申告時に提出できるようにしましょう。
課税対象となる金額は、譲渡所得から特別控除を差し引いた残額です。この課税譲渡所得に対し、所有期間によって異なる税率が適用されます。
| 所有期間 | 所得区分 | 所得税率 | 住民税率 |
| 5年超(長期) | 長期 | 15% | 5% |
| 5年以下(短期) | 短期 | 30% | 9% |
所有期間は売却した年の1月1日時点で判断します。長期譲渡所得であれば、譲渡所得金額×20%(所得税+住民税)で納税額を算出します。
長期・短期譲渡所得の違いや税率区分を丁寧に解説
不動産の所有期間が5年を超えていれば長期譲渡所得となり、税率が優遇されます。5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率が高くなります。
長期譲渡所得の計算例:
短期譲渡所得の計算例:
このように、所有期間によって税額が大きく異なるため、売却時期の判断も重要なポイントとなります。
不動産売却による確定申告では、居住用財産の3,000万円特別控除が大きなメリットとなります。適用にはいくつかの条件があり、主なポイントは以下の通りです。
適用漏れを防ぐには、売買契約書や登記事項証明書など、必要書類の準備を早めに進めることが重要です。申告手順は次の通りです。
特にe-Taxを利用する場合は、電子証明書やマイナンバーカードも必要となります。申告時期を過ぎないよう、余裕をもって進めることが大切です。
相続や贈与で取得した不動産を売却した場合、「取得費加算の特例」や「買換特例」を利用することで、譲渡所得税を軽減できます。この特例は、売却した年の前年または前々年に相続税を支払っている場合、支払った相続税の一部を取得費に加算できる制度です。
【取得費加算特例の主な必要書類】
買換特例は、一定の条件を満たして不動産を買い換えた場合に譲渡所得の課税を繰り延べることができる制度です。いずれも申告時に必要な書類を揃え、書類の不備や記載ミスがないか入念に確認しましょう。適用条件や利用可能なケースが限定されるため、詳細を国税庁サイトや専門家で確認するのが安全です。
特例を活用した申告事例を表で整理します。状況ごとのポイントを押さえることで、適切な制度選択が可能になります。
| ケース | 適用できる特例 | 注意点・ポイント |
| 自宅マンション売却 | 居住用財産3,000万円特別控除 | 売却後に住まなくなってから3年以内の申告が必要。売却先に身内が含まれる場合は不可。 |
| 相続した土地の売却 | 取得費加算特例 | 相続税を申告・納付していること。書類の準備と計算方法に注意。 |
| 住み替えのための自宅売却 | 居住用財産買換特例 | 新しく購入した物件が一定の要件を満たす必要。申告書作成時の記載内容に注意。 |
特例適用時は、税額計算や必要書類のチェックリストを作成し、申告漏れや記入ミスを防ぐことが重要です。自身での申告が不安な場合は、専門家相談も積極的に検討しましょう。
不動産売却の確定申告では、書類の不備や譲渡所得の計算ミスが多くのトラブルを招きます。例えば、登記事項証明書や売買契約書、譲渡所得の内訳書などの提出漏れ、取得費・譲渡費用の計算間違いが典型です。誤った情報は税務署からの指摘や手続き遅延の原因になりやすいため、下記の防止策が重要です。
書類やデータを一つずつ点検することで、トラブル発生リスクを大きく減らせます。
確定申告を怠ったり、申告内容に誤りがある場合、税務署から指摘や追加納税の通知が届くことがあります。この際に課される主なペナルティは無申告加算税と延滞税です。無申告加算税は申告忘れや遅延に対して課され、納付すべき税額の5~20%が追加請求されることがあります。延滞税は納税遅れに対して日数に応じて加算されます。
例えば、売却益が出ているのに申告しなかったり、必要書類の不備による審査遅延が該当します。こうしたリスクを避けるには、期限内申告と正確な記載・添付が必須です。また、特例や控除を適用する場合は、条件を満たしているか必ず確認しましょう。
申告ミスやトラブルを防ぐため、自己点検用のチェックリストを活用するのが効果的です。下記の表を参考に、申告前に一つ一つ確認しましょう。
| チェック項目 | 内容 |
| 必要書類の準備は完了しているか | 売買契約書、登記事項証明書、内訳書等 |
| 譲渡所得の計算は正確か | 取得費・譲渡費用・特例控除の反映 |
| e-Tax控除や添付書類の有無を確認済み | 電子申告の場合はアップロードも確認 |
| 申告期限を守れるか | 原則、翌年3月15日まで |
| 税理士や専門家への相談は必要ないか | 不明点があれば早めに相談 |
このように、一つひとつ丁寧にチェックを行うことで、申告トラブルや余計な追徴課税のリスクを大幅に減らせます。不動産売却の確定申告は複雑な要素も多いため、十分な準備と確認が安心につながります。
下記のテーブルでは、不動産売却に伴う確定申告を「自分で行う場合」と「税理士に依頼した場合」の違いをわかりやすくまとめています。
| 比較項目 | 自分で申告 | 税理士に依頼 |
| 費用 | 0円〜(郵送代など) | 5万円〜15万円程度 |
| 書類作成の手間 | 多い | 少ない |
| 手続きの難易度 | やや高い | 低い |
| ミスやリスク | 自己責任 | 専門家がサポート |
| 節税や特例の活用 | 限定的 | 幅広く対応 |
| サポート体制 | なし | 相談・対応可能 |
それぞれメリット・デメリットがあり、状況や希望により選択が異なります。
自分で確定申告を行う際は、下記の流れで進めるとスムーズです。
必要書類の準備
譲渡所得の計算
売却金額から取得費用・譲渡費用・控除額を差し引いて譲渡所得を算出します。
申告書の作成
国税庁の確定申告書等作成コーナーやe-Taxを利用して必要事項を入力します。
申告書類の提出・納税
e-Tax、郵送、または税務署窓口へ提出し、納付期限までに税金を納めます。
ミスを防ぐため、計算や添付書類に抜け漏れがないか丁寧に確認しましょう。
初心者が自力で申告を行う際の注意点とポイント
税理士へ不動産売却の確定申告を依頼する場合の費用は、物件や内容の複雑度によりますが、5万円〜15万円程度が目安です。
| サービス内容 | 詳細 |
| 書類作成 | 必要書類の収集・作成をすべてサポート |
| 節税アドバイス | 利用できる控除や特例の確認と適用 |
| 申告手続き | e-Taxや郵送まで専門家が対応 |
| 相談・説明 | 不明点や個別ケースへの的確なアドバイス |
| アフターフォロー | 修正申告や税務調査時の対応も可能 |
費用は依頼内容や不動産の種別により増減するため、事前に見積もりを取得することをおすすめします。
依頼費用の目安や依頼時の注意点を具体的に示す
確定申告を自分で行うか、税理士に依頼するかは下記を参考に検討しましょう。
自分で申告が向いているケース
税理士依頼が向いているケース
判断材料や成功・失敗事例を紹介し読者の意思決定を支援
自分の状況や知識レベルに応じて最適な方法を選ぶことが大切です。迷う場合は、無料相談や見積もりを活用し、納得のいく形で確定申告を進めましょう。
不動産売却による確定申告は、居住地を管轄する税務署で行います。申告方法は主に3つあり、窓口での提出、郵送、国税庁のe-Taxを使ったオンライン申告です。近年はe-Taxの利用者が増えており、パソコンやスマートフォンから手続きが可能です。
| 申告方法 | 特徴 |
| 窓口提出 | 税務署へ直接持参し相談も可能 |
| 郵送 | 必要書類を封入し税務署へ郵送 |
| e-Tax | オンラインで手続き、添付書類もデータ提出可能 |
自分に合った方法を選び、期限内(通常は翌年3月15日まで)に提出しましょう。
不動産の売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合、金額にかかわらず確定申告が必要です。損失が出た場合も特例や損失の繰越控除を受けるため申告が求められます。目安として、譲渡所得が50万円以下でも免除にはならないため注意してください。
確定申告が必要な主なケース
不動産売却に関しては「いくらから」ではなく、売却益の有無や特例の利用有無で判断します。
譲渡所得の計算は、「売却価格」から「取得費」「譲渡費用」を差し引いて算出します。その後、特例控除や経費を適用し、確定申告書第三表や譲渡所得の内訳書に記入します。
書類記入の主な流れ
書き方の詳細は国税庁のWEBサイトや作成コーナーが参考になります。間違いや漏れがないよう、必要書類を揃えて進めてください。
不動産売却に伴う確定申告で税理士へ依頼する場合、費用は物件や内容の複雑さによって異なります。一般的な相場は5万円~15万円程度ですが、複数物件や特例申請がある場合は20万円以上となることもあります。
| ケース | 費用相場(円) |
| 一般的な土地・建物 | 5万~10万円 |
| 特例・控除申請含む | 10万~15万円 |
| 複数物件・難解案件 | 15万~20万円超 |
費用がかかっても、複雑な計算や添付資料の対応を任せられるため、安心感があります。
居住用財産を売却した場合、3,000万円までの譲渡所得が控除される特例があります。適用条件は以下の通りです。
主な適用条件
全ての条件を満たすと、譲渡所得が3,000万円以下なら課税されません。適用の際は必要書類の提出が必須です。
e-Taxを使った不動産売却の確定申告は、パソコンやスマートフォンから簡単に申請できます。マイナンバーカードや電子証明書が必要で、申告書や譲渡所得の内訳書も電子データで提出します。
e-Tax利用のポイント
e-Taxは24時間利用可能で、還付金の受け取りも早くなります。
土地や建物を売却し、確定申告を行わない場合は重大なリスクがあります。追徴課税や延滞税、加算税が発生し、最悪の場合は刑事罰の対象となることもあります。
申告しない主なリスク
特例や控除を受ける権利も失うため、必ず期限内に正しく申告しましょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。