東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。
江東区の不動産売却・買取なら地元密着で豊富な実績の東京PM不動産
2025年11月18日
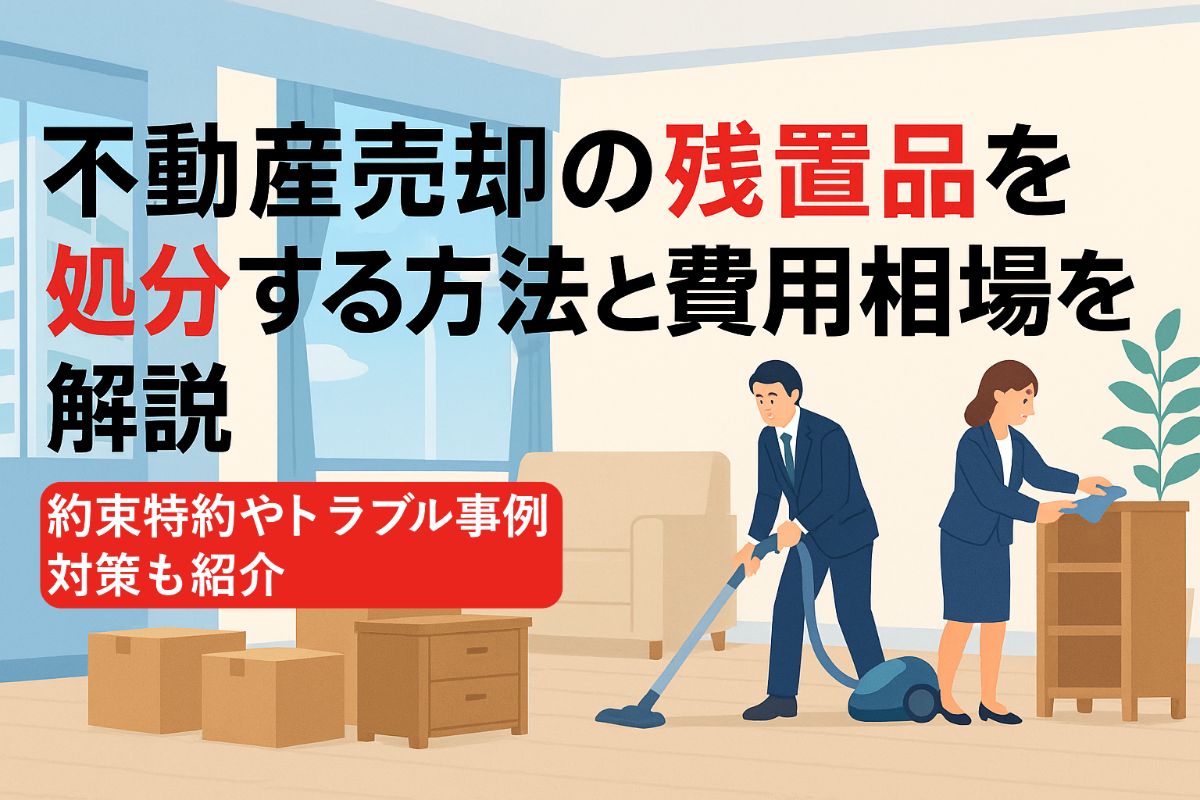
不動産売却の際、「残置品」の存在が思わぬトラブルや費用増加の引き金になることをご存じでしょうか。実際、中古住宅売買における残置品関連トラブルは全体の約1割を占め、年々その相談件数が増加しています。
「家財や家電が残ったまま売却したい」「処分費用が高額で困っている」と悩まれる方も少なくありません。例えば、一般的な一軒家の残置品処分費用は【10万円~30万円】とされ、物件の広さや残置品の種類によってはさらに高額になるケースも。さらに、契約書に残置品の取り扱いが明記されていない場合、引き渡し後に責任問題へ発展するリスクも指摘されています。
「想定外の費用やトラブルを避けたい」「スムーズな売却を実現したい」と考えている方は、ここで正しい知識と対策を身につけておくことが重要です。本記事では、売却現場で多発している残置品問題の実態から、最新の法的ポイント、具体的な処分方法や費用相場まで、専門家の見解や公的データをもとに徹底解説します。
最後までお読みいただくことで、ご自身のケースに合った最適な対処法や、損失を回避するための具体策が手に入ります。これから不動産売却を検討される方は、ぜひご一読ください。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
不動産売却時における残置品とは、売主が退去時に処分せずに物件内へ置いていった家具や家電、日用品などの総称です。売却が決まった後、引渡し時点で部屋に残っているものが「残置品」と呼ばれます。売主にとって不要となった物であっても、買主にとっては処理が負担となる場合が多いため、残置品の扱いは売買契約時の重要なポイントです。特に中古物件や相続物件では、残置品が多くなる傾向が見られます。
残置物との違いと混同しやすいケース
残置品と残置物は似ていますが、法律的な扱いや意味合いが異なります。一般的に「残置品」は売却や引渡し時点で置かれた家具・家電・家財などを指すのに対し、「残置物」は賃貸契約終了や所有者死亡などで放置された物を指します。下記のようなケースで混同しやすいため、注意が必要です。
このような場合、所有権や処分責任をめぐるトラブルが発生しやすいため、契約時に明確化しておくことが大切です。
残置品が発生しやすい売却シーン
残置品が発生しやすいのは以下のような売却シーンです。
売主が処分を後回しにしたり、費用や手間を考えて残したままにする場合が増えています。こうした残置品があると、買主が処分費用や手間を負担することになり、売却価格の減額や契約トラブルの原因となるため注意が必要です。
不動産売却時に発生する残置品や残置物は多岐にわたり、その判別がトラブル回避のポイントとなります。下記に主な種類と判別のコツをまとめます。
| 種類 | 具体例 | 判別ポイント |
|---|---|---|
| 家電 | 冷蔵庫、洗濯機、エアコン | 固定資産か備品か確認 |
| 家具 | ベッド、タンス、テーブル | 売却時に残す・持ち出すの合意有無 |
| 家財道具 | 食器、カーテン、寝具 | 生活用品か装飾品かで処分方法が変化 |
| 設備 | エアコン、給湯器、照明設備 | 設備表記載の有無を契約で明確化 |
| その他 | 自転車、ガレージ用品、工具 | 所有権の有無や不要品かを確認 |
家電の場合、エアコンや給湯器などは設備扱いとなるケースもあるため、契約書の設備表をしっかり確認することが重要です。また、家具や家財道具は処分方法や所有権の明確化がトラブル防止につながります。
家電、家具、家財道具、一軒家・マンションの特徴
一軒家とマンションでは、残置品の種類や量に違いがあります。
家電や家具の状態や、設置場所によっても処分方法や費用が異なります。特にエアコンや照明などの設備は、備え付けかどうかを契約で明記しておくと、売主・買主双方のトラブルを防げます。
不動産売却時は、残置品の種類や所有権、処分方法を正確に把握し、事前に確認・合意を取ることが円滑な取引につながります。
不動産売却時に残置品が放置されると、売主・買主双方に多くのリスクが発生します。家具や家電、エアコン、生活用品などが物件内に残されたままの状態は、不動産売却の価格低下や売買契約の遅延、さらにはトラブルの原因になることが多く、注意が必要です。残置品があることで「訳あり物件」と見なされる場合もあり、買主側が不安を感じるケースも少なくありません。売却前に残置品を適切に処分することは、スムーズな取引と高値売却のための重要なポイントです。
残置品が不動産に放置されたまま売却されると、さまざまなトラブルが発生します。以下の表で代表的なトラブル内容とその影響を整理しました。
| トラブル内容 | 発生原因 | 主な影響例 |
|---|---|---|
| 買主との追加交渉 | 物件に家具や家電が残ったまま | 価格交渉の長期化、値引き要求 |
| 売買契約の遅延 | 残置物処分の責任所在が不明確 | 引渡しの遅れ、売主・買主双方の負担 |
| 法的トラブル | 所有権の所在が不明 | 損害賠償請求や裁判・調停 |
| 撤去費用の負担増 | 事前説明や契約内容の不備 | 売主・買主いずれかに想定外の出費 |
| 買主による放置物処分 | 残置品の種類や状態が悪い | 買主が追加で業者手配・費用負担 |
特に「残置品とは何か」「処分費用は誰が払うか」などが曖昧なままだと、売買契約締結後に想定外の負担やトラブルに発展します。家電や家具、エアコンなどの設備機器は、残置品とみなされるかどうかも事前に確認しておくことが重要です。
所有権と責任の所在問題
不動産売却時の残置品に関する所有権や責任の所在は、契約書や特約で明確にしておく必要があります。所有権放棄書式や残置物特約の記載が不十分な場合、売主と買主の間でトラブルが発生しやすくなります。主な注意点を整理します。
売主が残置品の所有権を放棄しない場合
買主が勝手に処分できず、売主への連絡や同意が必要となります。
残置品撤去費用の負担者が不明確な場合
撤去費用は一般的に売主負担ですが、契約で買主負担となるケースも。費用負担の取り決めは必須です。
相続物件や賃貸物件の場合
元所有者や賃借人の所有権が残っていることもあり、第三者との間で権利関係が複雑化するリスクがあります。
所有権放棄や残置物特約の例文を活用する
契約書への明記や、残置物に関する特約の取り決め例を参考にして、責任の切り分けを徹底しましょう。
残置品が残っている中古物件や「訳あり物件」を購入する際は、購入後のトラブルを防ぐためにも事前のチェックが欠かせません。特に、下記のポイントに注意が必要です。
残置品の種類と所有権の確認
家具や家電、エアコンなどの設備が残っている場合、それらの所有権が誰に帰属するか明確にしましょう。
撤去費用と作業負担の把握
どちらが処分費用を負担するか、契約前に合意しておくことが大切です。
一軒家やマンションなど物件の種類によって、撤去費用や作業内容も異なります。
残置品の状態とトラブル履歴の確認
残置品が壊れていたり、過去にトラブルがあった場合は、購入後の追加費用や手間が増える可能性があります。
売買契約・特約条項の確認
契約書には残置品に関する条項がきちんと盛り込まれているか必ず確認し、不明点は専門会社や不動産業者に相談しましょう。
| 注意ポイント | チェック事項 |
|---|---|
| 所有権 | 残置品は売主か買主か、第三者か |
| 費用 | 撤去費用・処分費用は誰が支払うか |
| 状態 | 家具・家電・設備の動作や劣化状態 |
| 契約内容 | 残置品に関する特約や条項が明記されているか |
事前に専門業者へ相談し、残置品の取り扱いや撤去方法、費用相場などを把握することで、安全かつ円滑な不動産取引が実現できます。購入後のトラブルを避けるためにも、残置品の有無や状態についてしっかり確認しましょう。
不動産売却時に発生する残置品の処分は、売主の責任で行うことが一般的です。残置品とは、家電や家具、生活用品など、前所有者が物件に残したままの物を指します。適切な処分方法を知ることで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな売却を実現できます。ここでは売主が選べる全ての手段と、それぞれの特徴や注意点について詳しく解説します。
自己処理はコストを抑えやすい選択肢ですが、手間や時間がかかります。以下の手順とメリット・デメリットを確認してください。
具体的手順
メリット
デメリット
自己処理の主なポイント比較
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 少額~無料(一部有料処分あり) |
| 労力 | 非常に高い |
| 所要時間 | 数日~数週間 |
| トラブル防止 | 市区町村の分別・回収ルールを厳守する必要 |
専門業者への依頼は、手間をかけずに残置品を一括で片付けられる方法として人気です。次のポイントに注意しましょう。
依頼時のポイント
費用相場
業者依頼の主なメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 短期間で大量の残置品を一括処分できる | 費用が高額になることがある |
| 重い家具や家電もプロが安全に搬出 | 業者選びを誤るとトラブルの元 |
| 清掃や特殊な処分もまとめて依頼可能 | 個人情報の取り扱いに注意 |
近年、一部の不動産会社では「残置品あり物件」としてそのままの状態で買取や売却が可能な場合もありますが、必ず条件やリスクを理解しましょう。
主な条件
注意点
残置品あり売却の主な比較表
| 買主 | 撤去費用負担 | 契約条件明記 | 価格への影響 |
|---|---|---|---|
| 一般個人 | 売主 | 必須 | マイナス大 |
| 買取業者 | 業者 | 必須 | マイナス小~中 |
残置品処分は方法を正しく選ぶことでトラブルを防ぎ、スムーズな売却へと繋がります。各手段の特徴やポイントを押さえ、安心して不動産売却を進めてください。
不動産売却時に発生する残置品の処分は、トラブル防止や売却スムーズ化のためにも事前の把握が重要です。特に残置品の処分費用や負担者については、予想外の出費や揉め事につながりやすいため、明確なルール設定と交渉が不可欠です。主な残置物には家具、家電、生活雑貨などがあり、それぞれ処分方法や費用相場が異なります。ここでは、各種残置品の処分費用目安、費用負担者のルール、コスト削減のコツを詳しく解説します。
残置品の種類によって処分費用は大きく異なります。以下のテーブルは主な残置品別の処分費用目安をまとめたものです。
| 残置品の種類 | 処分方法 | 費用目安(1点あたり) |
|---|---|---|
| ソファ・ベッド | 粗大ごみ・業者回収 | 3,000~10,000円 |
| 冷蔵庫・洗濯機 | リサイクル家電回収 | 5,000~7,000円 |
| エアコン | リサイクル家電回収 | 4,000~7,000円 |
| タンス・テーブル | 粗大ごみ・業者回収 | 2,000~8,000円 |
| 生活雑貨 | 一般ごみ・業者回収 | 1,000円~ |
| 一軒家全体 | 片付け業者一括処分 | 80,000~200,000円以上 |
残置品の量や状態によって費用は異なります。特にリサイクル家電は法律に基づく処分が必要で、自治体の粗大ごみとは別の手続きが必要です。複数点まとめて依頼することで割安になる場合もあります。
残置品処分費用の負担者は、原則として売主が責任を持つケースが多いですが、契約内容や交渉次第で変動します。トラブル予防のためには、契約書に具体的な記載を行うことが重要です。
交渉の際は、残置品の現状や処分費用の見積もりを事前に確認し、双方の納得が得られる形で契約内容を確定させることが大切です。
残置品の処分にかかるコストを抑えたい場合、いくつかの実践的な方法があります。
リサイクルショップやフリマアプリを利用する
まだ使える家具や家電は買取査定に出すことで、逆に現金化できることもあります。
自治体の粗大ごみ回収を活用する
費用が安く済みますが、回収日が限られるため計画的な申し込みが必要です。
複数業者から見積もりを取る
業者によって料金体系が異なるため、比較することで最適な選択ができます。
家財道具処分業者に一括依頼する
時間や手間を最小限にしつつ複数品目をまとめて処分でき、結果的に費用を抑えられるケースも多いです。
知人や団体への譲渡
必要とする人がいれば無料または格安で引き取ってもらえる場合があります。
これらの方法を組み合わせて検討することで、残置品の処分にかかる経済的・時間的負担を大きく軽減できます。事前の準備と情報収集が成功のカギとなります。
不動産売却時には、残置品をめぐるトラブルを防ぐために、売買契約書へ残置品特約を明記することが重要です。特約の記載例としては、以下のような内容が挙げられます。
| 特約例 | 内容 |
|---|---|
| 残置品引渡し特約 | 売主が指定の家具・家電を残したまま引き渡すことを買主が了承する旨 |
| 残置品撤去特約 | 売主が全ての残置物を撤去し、空室状態で引き渡すことを明記 |
| 残置品処分費用負担特約 | 残置品の撤去・処分費用を売主・買主いずれが負担するかを明示 |
このような特約を明記することで、売主・買主双方の認識のズレを防ぎ、後のトラブルを回避できます。また、残置品にエアコンや大型家具が含まれる場合も、具体的な品目を記載することで、引渡し時の混乱を防ぐ効果があります。
残置品の扱いについては、売主・買主の事前合意が不可欠です。合意形成の際は、次のポイントに注意しましょう。
特に中古物件や相続物件の場合、残置物の所有権や撤去義務に関する誤解が生じやすいため、専門業者や不動産会社への相談も有効です。細かい事項まで合意し、記録を残すことで安心して取引を進められます。
残置品の対応を曖昧にすると、以下のような法的リスクやトラブルが発生する可能性があります。
| リスク事例 | 内容 |
|---|---|
| 所有権の曖昧化 | 残置物の所有者が不明確で、勝手に処分すると法的責任を問われる場合がある |
| 費用負担のトラブル | 撤去費用について双方の認識が異なり、後から請求される |
| 特約未記載による紛争 | 契約書に記載がないことで、引渡し後に「残置物撤去義務」が争点となる |
トラブルを回避するには、契約書へ残置品に関する詳細な特約を必ず盛り込むこと、引渡し前の室内確認を行い、残置物の有無と内容を写真などで記録することが重要です。また、撤去が必要な場合は信頼できる処分業者を利用し、処分証明書を取得しておくことで後日の証拠にもなります。これにより、売主・買主双方が安心して不動産取引を進めることができます。
不動産売却時、残置品は原則として売主が撤去し、物件を空の状態で引き渡すのが一般的です。家具や家電、生活用品などが残ったままの状態は「残置物あり物件」と呼ばれ、買主から敬遠されやすくなります。引き渡し前に売主が責任を持って処分することで、スムーズな売買契約の成立が期待できます。ただし、事前に買主と協議し、残置物の一部を譲渡するケースもあるため、契約内容を明確に確認しておくことが重要です。
通常、残置物の撤去費用は売主が負担します。買主が残置物の処分を希望した場合など、例外的に買主側が費用を一部または全額負担するケースもあります。費用負担については契約書で明確にしておくことで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。
| 費用負担者 | 主なケース |
|---|---|
| 売主 | 原則・通常の売買契約 |
| 買主 | 特別な合意がある場合 |
| 双方で分担 | 契約で取り決めた場合 |
残置品の所有権は原則として売主にあります。買主や第三者が勝手に撤去することは、所有権の侵害となるため避けるべきです。撤去前には必ず所有者の同意を得て、内容やタイミングを明確にしておきましょう。特に相続や賃貸物件では所有権や責任の所在が複雑化しやすいので、慎重な対応が求められます。
残置品あり物件を購入する際には、処分費用や手間、予期せぬ廃棄物の存在などがリスクとなります。撤去費用が高額になる場合や、残置物に所有権が残っているとトラブルの原因となる可能性があります。購入前に残置物の内容や所有権、処分費用の負担者をしっかり確認することが重要です。
契約書に残置品特約がない場合、売主が残置物を撤去するのが原則です。特約未記載の場合は、引き渡し前に双方で処分方法や費用負担について合意し、速やかに書面にて取り決めを行いましょう。後々のトラブル防止のため、証拠として残しておくことが大切です。
残置品処分は、売買契約締結後から引き渡し前までに完了させるのが理想です。効率的に進めるためには、以下の流れが推奨されます。
事前にスケジュールを立て、無駄な費用や手間を抑えることがポイントです。
エアコンや大型家電の処分にはリサイクル法が適用され、専門業者への依頼やリサイクル料金が発生します。自治体による回収は不可の場合が多く、事前に費用や手続き方法を確認しておくことが重要です。動産としての価値がある場合は、買取業者の活用も視野に入れると良いでしょう。
土地売買の場合、古家や残置品がある状態で売却されるケースもあります。解体や残置物撤去費用を誰が負担するか明確にすることが重要です。買主が更地渡しを希望する場合、売主に撤去義務が生じます。契約前に現地確認と費用見積もりを実施し、トラブル防止策を講じておきましょう。
一軒家の売却時は、家財道具や家具類の処分費用が高額になることがあります。効率的な処分方法として、リサイクルショップや不用品回収業者の利用、廃棄物の分別処理が挙げられます。費用相場や処分業者の信頼性を比較し、コストを抑える工夫が求められます。
残置品の処分費用が譲渡所得の必要経費として認められる場合があります。ただし、経費算入には領収書の保存や明確な処分記録が必要です。節税目的で処分費用を計上する際は、税理士など専門家に相談し、税務上の条件をきちんと確認しましょう。
不動産売却を成功させるには、売却前の残置品整理が不可欠です。まず物件内の家財や家電、家具、エアコンなどをリストアップし、必要なものと不要なものに分類します。特に中古物件では、残置物の有無が売却価格やスピードに大きく影響します。不要品はリサイクル業者や不用品回収業者に依頼し、処分費用や対応可能な品目を比較することが大切です。
費用相場やサービス内容を複数の会社で比較検討し、信頼できる業者を選びましょう。下記に主なポイントを表形式でまとめます。
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 不要品リスト | 家具・家電・生活用品の有無を確認 |
| 業者の選定 | 見積もり・対応範囲・口コミを比較 |
| 費用の把握 | 処分費用とリサイクル費用の内訳確認 |
| 契約内容の確認 | 回収・処分方法や追加料金の有無確認 |
売買契約書には残置品に関する条項を明記しましょう。売主・買主のどちらが処分を行うのか、また残置物がある場合の責任範囲や費用分担をはっきりさせることが重要です。
契約書作成時に必ず確認したいポイントをリストで整理します。
これにより、トラブルや追加費用の発生リスクを未然に防ぐことができます。
売却活動中の内覧時には、室内をできる限り整理整頓し、残置物を最小限にしましょう。見学者に好印象を与えることが、成約率の向上につながります。
主な内覧対策は以下の通りです。
残置品が残っている場合は、どの程度まで引き渡し時に撤去するか、内覧時に説明しておくと安心感につながります。
実際の売却現場では、残置品をめぐるトラブルが少なくありません。例えば、売却後に残置物の撤去費用をめぐって争いになるケースや、残置物が理由で買主から値引き交渉を受ける事例もあります。
成功事例としては、事前に詳細な残置品リストを作成し、売主・買主双方で合意した内容を契約書に明記したことで、後からの誤解やトラブルを防げたケースがあります。また、残置品の状態や種類を写真で記録し、証拠として残しておくことも有効です。
| ケース | トラブル内容 | 事前対策 |
|---|---|---|
| 家具残置 | 買主と撤去費用トラブル | 契約書に撤去費用分担を明記 |
| 家電の動作不良 | 買主からのクレーム | 事前に設備・残置品を分けて明記 |
| 私物放置 | 引渡し後の連絡 | 引渡し前に写真記録&合意 |
買取業者の活用や「現状渡し」での売却は、残置品処分の手間や費用を大幅に削減できる方法です。特に急いで売却したい場合や、家財道具が大量に残っているケースでは有効です。
現状渡しを希望する場合は、買主との交渉で条件を明確にし、不要品の所有権放棄についても書面で残すことが大切です。買取専門業者は、残置品込みでの査定や、家財道具の一括処分サービスを提供していることが多く、スムーズな売却が実現できます。
| 方法 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|
| 買取業者利用 | 残置品ごと一括売却が可能 | 査定額が相場より低くなることもある |
| 現状渡し契約 | 処分不要で手間とコスト削減 | 契約内容を明記しトラブル回避が必須 |
このような方法を活用し、効率よく不動産売却を進めましょう。
東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。江東区や東京都江東区の不動産売却やマンション、一戸建て、土地の査定、売却買取のご相談をお考えの方は、地元で豊富な実績とノウハウを持つ当社にお任せください。
当社では賃貸/売買仲介事業・賃貸管理事業・収益不動産事業・買取再販売事業・サードライフ高齢者施設の事業を行っております。不動産売却や不動産投資、賃貸に関してお悩みがありましたら、まずはお気軽にご相談ください。

社名:株式会社東京PM不動産
住所:東京都江東区三好2丁目17-11
電話:03-5639-9039
会社名・・・株式会社東京PM不動産
所在地・・・〒135-0022 東京都江東区三好2丁目17-11
電話番号・・・03-5639-9039
株式会社東京PM不動産は、江東区を中心に清澄白河や住吉エリアでの不動産売却や不動産投資、賃貸のサポートを行っています。地元密着で豊富な実績とノウハウを持つ同社は、マンション、一戸建て、土地の査定や売却買取のご相談を専門としています。お客様のニーズに合わせた最適な価格設定のアドバイスや、不動産の価格や成約に関するノウハウは、同社の強みとして多くのお客様からの信頼を得ています。また、不動産売却に関する税金や節税のガイドも提供しており、お客様の利益を最大化するためのサポートを行っています。